ミンチ解体から最新の環境配慮型解体へ──解体工事の進化と法制度の歩み
かいたいコラム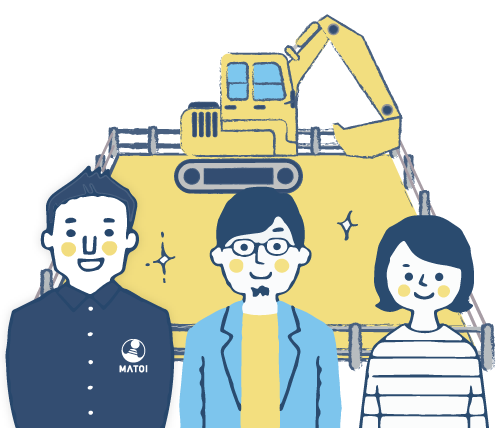
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
解体工事では、騒音・振動・粉じんといった問題が常に課題として挙げられます。環境対策が社会的課題として大きく取り上げられるようになった現在では、なおさらです。
この社会の動向を受けて、解体工事のあり方も大きく変化してきました。
かつて主流だった「ミンチ解体」と呼ばれる方法は現在では禁止され、建設リサイクル法などの法整備とともに環境配慮型の解体方法が行われています。
今回はミンチ解体から、環境配慮型への解体方法の変遷を取り上げます。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事をお請けしている解体業者です。“よく働くマトイ” をモットーに解体工事はもちろんのこと、それに付随したご相談等にも対応しています。
建物の解体のご検討を始めた段階から、どうぞお気軽にお問い合わせください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
解体工事のマイナスイメージを生んだ「ミンチ解体」
以前は解体工事の主流であったミンチ解体。でも、それによる騒音・振動・粉じんによる環境負荷は大きなものでした。
解体工事のイメージ
「近所の建物が解体される」と聞くと、「あぁ、しばらくはうるさいな」「工事が終わるまで洗濯物は外に干せない」などと近隣の方々は思うことでしょう。
かつて行われていたミンチ解体では、近隣の方々が受ける負担や印象は現在よりも大きなものでした。
そのイメージを生んだミンチ解体
そこで、ミンチ解体について詳しく説明します。
ミンチ解体の工法
ミンチ解体を一言で説明すると、「重機を使って建物を一気に壊していく」解体方法です。
重機のアームに解体専用のアタッチメントを付けて、建物を壊していきます。そして解体によって排出された瓦礫は、分別することなく重機などで細かくして運搬します。
分別しないため、それに要する時間は必要ありません。そのため、同じ大きさの建物を解体するのにも、現在の解体方法よりも早くできました。
「ミンチ解体」は解体方法の1つです。さらに、実際に解体工事を進めるとき、さまざまな工法を組み込みながら解体を行います。その工法を含め、知っておきたい解体工事の基礎知識をこちらのコラムにまとめています。どうぞ、ご覧ください。
ミンチ解体で得られていたメリット
かつてミンチ解体が行われていたのには、次のようなメリットがあるとされていたためです。
〇工期が短い
現在のように分別しながらではなく、重機を用いて一気に建物を解体していくため、その分、短い工期でできました。
〇人件費や作業コストが抑えられる
足場の設置や手作業による分別を行わないため、少ない作業員数や比較的短い作業時間できました。そのため、人件費や作業コストが抑えられました。
〇廃材処理が簡略
重機を使って建物の建材を細かく砕くため、廃材の収集や運搬がしやすく、リサイクル工程の簡略化につながると考えられていました。
ミンチ解体のメリットとして最初に挙がったのが「工期の短さ」でした。こちらのコラムで、一般的な工期のとらえ方等を説明しています。参考にお読みください。
ミンチ解体の問題点
前述のようにかつてはメリットがあるとされていたミンチ解体ですが、次に挙げるようなことが社会問題として浮き彫りにされてきました。
〇廃棄物の分別が困難
ミンチ解体では、木材・金属・コンクリートなど本来リサイクル可能なものが混在した状態に。そこからの分別は難しく、リサイクルが困難でした。
〇アスベスト等の有害物質の飛散リスクが高い
かつての建物にはアスベストが多用されていました。また、有機溶剤などを取り扱っていた工場なども含めて、解体によって人々の健康に害を及ぼす物質が飛散する可能性があります。
それらの物質も一緒に破砕するミンチ解体では、作業員や近隣住民への健康への影響の可能性がより高い状況でした。
〇環境負荷が大きい
リサイクルが困難な廃材は埋め立て処分になるため、その量が増加。それによる環境負荷が大きくなり、問題となりました。
〇法令違反となる
建設リサイクル法が2000年に制定され、特定建設資材(コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別や再資源化が義務付けられるようになりました。
そして同法が完全施行された2002年にはミンチ解体は事実上禁止となりました。さまざまな建設資材が混在した状態のまま廃棄すると法令違反となって、罰則の対象となります。
〇施主の立場の人にも責任の可能性
違法解体を依頼・容認した場合、施主の立場になる人にも罰金が科される可能性があります。
建設リサイクル法は、解体工事や建築工事等を行う場合、知っておくべき法律です。こちらのコラムでも、そのポイントを説明していますので、お読みください。
ミンチ解体の違法性と罰則
建設リサイクル法によって禁止されているミンチ解体ですが、これに違反する罰則として50万円以下の罰金がかせられます。
ミンチ解体が認められる例外
このようにミンチ解体は禁止されていますが、次の場合は一部例外として認められるケースがあります。
ただし、例外となるか否かは、自治体や監督官庁に事前に確認をとる必要があります。また、例外となったとしても、廃棄物処理法の適用は受けるため、適切に処理することが大切です。
〇建設リサイクル法の対象外となる工事
法令で定める「特定建設資材の使用面積・延べ床面積」に満たない、規模が小さい工事。木造住宅の場合は、床面積80㎡未満の工事。
〇特定建設資材を使用していない建物の工事
特定建設資材とされるコンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが使われていない建物の解体工事。
〇災害等による緊急解体
地震や火災などによって建物が激しく損壊し、分別が不可能な状態の場合、行政の判断によって例外となることがある。
〇建築物以外の工作物の解体
塀、看板、仮設物などの工作物は分別義務の対象外となる場合がある。
廃棄物処理法および解体工事に際しての廃棄物の取り扱いについて、こちらのコラムで説明しています。廃棄物処理法は建設リサイクル法とともに解体工事に際して施主様も知っておきたい法律ですので、どうぞお読みください。
環境に配慮した分別解体への流れ
社会の環境に関する意識が徐々に変化してくるなか、前述のようなミンチ解体の問題点も社会の大きな環境問題を引き起こしていました。それは産業廃棄物が増加し、適切なリサイクルや処分が行えなかったり、悪質な業者による不法投棄が増加したり、といったことでした。それによる環境悪化も深刻なものになっていました。
解体工事の依頼に際しては、「どんな業者に頼めばいいのか」と不安を感じる方も多いことでしょう。そんなときは、どうぞマトイにお問い合わせいただき、マトイの対応を直接感じ取っていただけたら幸いです。
ちょっとした質問でも、丁寧にわかりやすく対応させていただきます。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
制度とともに変化してきた解体方法
そうしたなかで建設リサイクル法ができて、ミンチ解体から分別解体へと大きな推進力となっています。
建設リサイクル法施行とその概要
改めて建設リサイクル法について説明しておきましょう。
この法律の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」というもので、2000年に制定され、2002年に全面施行されました。
産業廃棄物の増加や不法投棄が問題となるなか、資源の有効利用と環境保全を目的にした法律で、これによって分別解体と再資源化が義務づけられることになりました。なお対象となる特定建設資材は、すでに記しているようにコンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートなどです。
対象となる工事の基準と義務および手続きは以下のとおりです。
〇対象工事の基準
・床面積80㎡以上の解体工事。
・床面積500㎡以上の新築・増築工事。
・請負代金1億円以上の修繕もしくは模様替え工事。
・請負代金500万円以上の建築物以外の工作物の工事。
〇義務と手続き
・分別解体と再資源化の実施義務。
・工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出。
・契約書に分別、再資源化費用を明記。
・解体工事業者の都道府県知事への登録制度。
・主務大臣による基本方針の策定に対応。
分別解体の義務と罰則
建設リサイクル法による義務を果たさなかった場合、以下のような罰則が科せられます。なお、違反の内容が悪質な場合は、事業停止命令や登録取消などの行政処分もあり得ます。
〇対象となる建設工事の届け出を怠った場合……罰金20万円以下
〇対象となる建築工事の変更の届出を怠った場合……罰金20万円以下
〇対象となる建設工事の届け出等について行政から変更命令が出た場合……罰金30万円以下
〇分別解体等義務の実施命令が行政から出た場合……罰金50万円以下
地方自治体による指導・監視体制の強化
また各自治体は、建設リサイクル法の確実かつ適正な運用に向けた指導・管理体制を強化し、現場ごとの法令の順守を徹底しています。それによって環境保全・安全確保・社会的信頼の維持を図っています。
その具体的な取り組みは、次に通りです。
〇現場パトロールの実施
環境省・国土交通省・厚生労働省が連携した全国一斉パトロールを、毎年秋に全国規模で実施。
さらに自治体の建設リサイクル法担当部局や環境部局、特定行政庁である労働基準監督署が合同で現場を巡回します。
このときの確認事項は次のとおりです。
・分別解体、再資源化の実施状況。
・届け出の有無とその内容。
・標識掲示の有無。
・アスベストやフロンなどの適正処理。
・労働安全衛生法や石綿障害予防規則の順守。
〇行政指導および是正勧告
・パトロールをした現場に違反が確認された場合、口頭指導、文書指導、そして是正命令などが行われます。
〇届け出および登録の審査
・解体工事業者としての登録申請や変更届け出を審査し、不備ついて補正指導を行います。
・虚偽の届け出内容があった場合は、登録抹消や罰則の対象となります。
〇周知・啓発活動
・自治体のホームページや説明会などを通して、施主や業者に向けて法令の周知徹底を図ります。
廃棄物処理法との連携
このように建設リサイクル法によって、ミンチ解体から環境に配慮した分別解体へと解体方法は変わりました。そして解体工事によって発生した廃棄物に対しては、建設リサイクル法と廃棄物処理法が連携して解体工事の適正な処理と再資源化を支えています。
それぞれの法律の役割は次のとおりです。
〇建設リサイクル法の役割
対象:一定規模以上の建設工事(解体・新築・修繕など)。
目的:建設資材の分別と再資源化。
特徴:
・工事前に都道府県知事への届け出、
・解体業者の登録制度、
・発注者との契約書に費用を明記、等を行う。
〇廃棄物処理法の役割
対象:建設廃棄物を含めるすべての廃棄物。
目的:廃棄物の適正処理・不法投棄防止・環境保全。
役割:
・施主や元受け業者の排出事業者責任、
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)および産業廃棄物処理の委託契約時は契約締結、
・収集運搬・中間処理・最終処分を行う処理業者の許可制、等を行う。
廃材の処分には、上記の2つの法令のほか、石綿障害予防規則、家電リサイクル法なども関係します。こちらのコラムで、それら関連する法令や廃材の分類や処理方法について取り上げています。併せてお読みください。
解体工事のイメージを塗り替える環境配慮型解体のポイント
現在、解体方法は資源の再利用・再資源化を促進しつつ、環境負荷を最小限に抑える環境配慮型解体となっています。そのポイントについて説明します。
分別解体による資源循環の促進
分別解体を徹底して行うことから、廃棄物量を削減して埋め立て処分量を削減します。さらに分別したコンクリートや木材、金属、アスファルトなどを再生砕石、再生木材チップ、再生アスファルト等に加工し再使用していくことで、資源の循環を促進します。
騒音・振動・粉じんの抑制技術
騒音・振動・粉じんの抑制対策は、現場の近隣の人々の暮らしや周辺環境保全に不可欠なものです。次のようなことで抑制を行います。
〇騒音抑制に対して
・低騒音型建設機械の使用。
・防音パネルや仮囲いの実施。
・近隣住民の生活リズムを配慮した作業時間。
・打撃音を伴わない解体工法を採用。
〇振動抑制に対して
・低振動型機械の導入。
・振動や騒音を抑えた工法(圧入工法:サイレントバイラ―)の導入。
・軟弱地盤の場合、地盤改良による振動伝播の抑制。
・振動のモニタリング。
〇粉じん抑制に対して
・散水やミスト噴霧装置の導入。
・防塵ネットや養生シートの設置。
・集塵機の設置。
・粉じん濃度の測定。
有害物質の適正処理
解体工事では、アスベスト、PCB、鉛・カドミウム・水銀、フロン・ハロン、ダイオキシン類などの有害物質が発生する可能性があります。それらを関係法令に基づいて安全、かつ環境に負荷の少ない方法で処理します。
アスベスト含有建材やアスベストを使用している建物を解体する際には、事前調査を始め、使用レベルに応じてアスベストの飛散防止を配慮した方法で除去します。その方法等について、こちらのコラムで説明していますので、お目通しください。
地域連携と社会的責任
解体を含めた建設工事においては、環境負荷の低減、住民および作業員の安全と安心の確保、緊急対応計画の整備等の配慮と対策を行います。
これらの取り組みは業者のみでなく、近隣住民とのコミュニケーションを図りながら、連携して行っていきます。
環境配慮型解体の流れ
環境配慮型解体は、分別解体をはじめとした前項で説明したような配慮を現場の状況に合わせて取り入れながら行っていきます。
解体工事としての流れは一般的なものとほぼ同じですが、アスベストをはじめとした有害物質の事前調査や対策、分別・再資源化、地域への配慮などが強化されています。
事前調査
・建物の構造、使用している建材、有害物質(アスベストやフロン類など)およびそれらを含んだ建材や吹付などの有無を事前に調査。
解体工事に際しての事前調査には家屋調査とアスベスト調査があります。こちらのコラムで説明していますので、こちらもどうぞお目通しください。
解体計画の策定
・解体計画書を作成し、有害物質含有建材等の除去などを行う場合など、必要に応じて労働基準監督署や自治体に届け出る。
・近隣住民への挨拶回りや告知、解体工事の規模に応じて説明会などを実施。
養生・防音・防塵対策
・足場を設置し、養生シートや仮囲いなどを設置。周辺環境に応じて養生シートを防音や防塵などの機能に特化したものを選択。
・防塵、防音、振動対策として、散水装置や低振動型重機を使用し、静的破砕工法も取り入れる。
有害物質の除去
・アスベストや重金属類を含む建材を使用している場合は、決められた方法で除去。
・その際、作業環境測定および除染結果を記録(写真・分析)。
分別解体の実施
・解体を進めながら、建材を木材、金属、コンクリート等の種類ごとに分別。
・再資源化が可能なものはリサイクルへ回し、廃棄物は決められた方法で処理を進める。
廃材の搬出と再資源化処理
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行し、処理を業者へ委託。
・処理場の確保と搬出記録を管理。
整地・完了確認
・解体工事完了後の土地を整地し、清掃等を行って安全な状態に整える。
・施主や自治体による確認を受けて完了。
まとめ
今回はかつて行われていたミンチ解体から、現在、行われている分別解体、そして環境により配慮する環境配慮型解体について説明を進めてきました。
ミンチ解体を簡単に表現すると、すべてを粉々にして廃棄する方法でした。一方、分別解体では解体した建材をリサイクルするため、廃棄物の量を削減し、CO2も削減。そして解体したものを新たな形にして“活かす”ということを行っています。
確かに現場での分別作業は大変です。しかし、分別作業が環境改善に直結する作業であると、私たちは受け止めています。
環境保全に向けて“手間を惜しまず”、日々の作業に取り組んでいます。同時に、効率化することで環境にも施主様にも負担を減らせるものがあります。
例えば、解体工事前の事前調査の1つであるアスベスト事前調査。当社では、営業職が建築物石綿含有建材調査者の資格を有し、また現場には専任の石綿作業主任者を配置して作業を進めています。さらに廃棄物の処分では、産業廃棄物収集運搬許可証を取得して、自社で廃棄物を処理場へ運搬しています。
こういったことから、他社に委託する部分を自社で行うことで業務の効率化が図れています。これは、最終的に施主様のご負担の軽減につながります。
また、「マトイ無料ご相談・お見積りフォーム」をご都合の良いときにご利用いただくことで、いつでもアクセスしていただけます。どうぞ、お気軽にご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
古民家の梁や柱は宝物! 古材買取のメリット
Next
ツーバイフォー解体の費用・日数・注意点|知っておきたい構造の特徴









