補助金等でおトクに建物解体! その利用方法と情報の取り方
かいたいコラム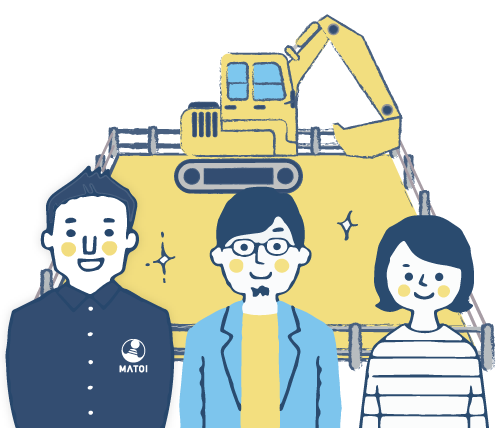
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
自治体や地方公共団体などが事業者や個人に対して支給する補助金や助成金。これらは建物の解体工事に活用できるものも自治体によってあります。返済の必要がないことから、経済的な負担が軽減されるために、できれば活用したいもの。
今回は補助金等の利用方法や補助金に関する情報の取り方などについて説明します。
“よく働くマトイ”では解体工事をはじめ、それに付随したことのご相談等にも対応させていただいていますので、どうぞお声掛けください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の建物解体の補助金をご紹介
「補助金を活用することで、どれだけおトクになる?」という点を、まずは知りたいですよね。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を活動エリアとして解体工事を行っています。そこで、これら1都3県において建物の解体に使える補助金等の一部をご紹介します。
東京都内の補助金等
東京都には23区のほか26市、そして伊豆諸島などにある町村を含めると62の市区町村があります。そのなかの一部ですが、家屋の解体時に活用できる補助金等を備えている次の3区の制度をご紹介します。
【東京都墨田区の補助金等】
○事業の名称
老朽危険家屋除却費等助成制度
○事業の概要
区内の老朽危険家屋等の所有者等に自主的な対応を促すことで、除却の促進や跡地の有効活用等を図り、倒壊等の事故や火災等を防止し、区民の安全・安心な暮らしを確保。
・住宅地区改良法に規定する不良住宅を対象とした除却費の助成。
・土地無償貸与(原則10年間)を前提とした除却費の助成。
○助成金額
・不良住宅の除却
除却費用の2分の1。上限額50万円(無接道敷地の場合は上限額100万円)。
・土地無償貸与前提の除却
除却工事に要した費用で上限200万円まで助成。
○担当部署
都市計画部危機管理担当安全支援課安全支援・空き家対策係
【東京都板橋区の補助金等】
○事業の名称
老朽建築物等除却費助成事業
○補助の概要・目的
板橋区より特定空き家等または特定老朽建築物として認定された建物は、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成。
○補助の金額
・建物の除却は、その延べ床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じた額。上限額100万円。
・工作物等の除却では、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じた額。上限額100万円。
・建築基準法第43条(接道義務:建築物の敷地は原則、2m以上道路に接していなければならない)に該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8として交付。上限額200万円。
○担当部署
都市整備部建築安全課老朽建築物対策係
【東京都西東京市の補助金等】
○事業の名称
木造住宅耐震改修等助成制度
○事業の概要
「災害に強いまちづくり」推進の一環として、1981(昭和56)年5月31日以前に建築され、所有者が居住している木造住宅の耐震改修または除却(建て替えを伴うものを含む)の費用を一部助成。
○助成金額
・耐震改修に対しては要した費用の2分の1以内。上限額90万円。
・除却(建て替えを伴うものを含む)に要した費用の3分の1以内。上限額30万円。
○担当部署
西東京市まちづくり部住宅課住宅係
埼玉県内の補助金等
埼玉県には、63の市町村がありますが、なかには補助金等の制度をもつ自治体、もたない自治体があります。以下はその一部ですが、ご自身が所有する家屋が所在する地域の補助金等の事情を確認しましょう。
【埼玉県蕨市の補助金等】
○補助金の名称
蕨市老朽空き家等解体補助金交付
○補助の概要・目的
老朽化した空き家等の安全な管理を図ることで、倒壊等による第三者への被害を未然に防ぎ、良好な生活環境の保全と安全で安心なまちづくりの推進を目的に、空き家等の解体の費用の一部を補助。
○補助の金額
空き家等の解体工事に要した費用(消費税を除く)として市長が認める額に、3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)。上限額30万円。
○担当部署
都市整備部建築課建築開発指導係
【埼玉県上尾市の補助金等】
○補助金の名称
空き家除却補助金
○補助の概要・目的
空き家対策の一環として1年以上使用されていない空き家を除却したとき、空き家の所有者、管理者、もしくは相続人等に対し、その費用の一部を負担。
○補助の金額
対象費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)を補助。上限額30万円。
市の調査によって対象となる空き家が「不良住宅」と判定された場合は、対象費用の5分の4を補助。上限額50万円。
○担当部署
交通防犯課
【埼玉県飯能市の補助金等】
○補助金の名称
木造住宅の除却工事補助金
○補助の概要・目的
地震に伴う木造住宅の倒壊による被害を最小限に食い止め、安全なまちづくりを目指すために、1981(昭和56)年5月31日以前に工事に着手した木造住宅の除却を行った場合に経費の一部を補助。
○補助の金額
除却工事に要した費用の23%以内(1,000円未満切り捨て)。
限度額:市内事業者が施工する場合30万円、市街事業者が施工する場合20万円。
○担当部署
建設部建築課
神奈川県内の補助金等
以下は神奈川県で補助金等の制度をもつ一部です。神奈川県内には33の市町村があり、ここに挙げたほかにも家屋解体に活用できる補助金等の制度を有する自治体があります。
【神奈川県横浜市の補助金等】
○補助金の名称
住宅除却補助制度
○補助の概要・目的
1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を得て着工され、横浜市の耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組工法)に対して、解体工事に要する費用を補助。(長屋、共同住宅の「空き家・貸家」は「倒壊の恐れがある空き家」と判定されたものを除き補助対象外)
○補助の金額
補助法減額 課税世帯20万円、非課税世帯40万円(床面積、見積り金額による補助額設定あり)
○担当部署
建築局建築防災課耐震事業担当
【神奈川県横須賀市の補助金等】
○補助金の名称
A 空き家解体費用助成事業(老朽化や痛みが激しい空き家)
B 旧耐震空き家解体助成事業(旧耐震基準の空家)
○補助の概要・目的
古くなって老朽化した空き家の老朽度や築年数などの状況に応じ、A・Bの2種類の事業によって空き家対策を推進。
○補助の金額
A 解体工事費用の2分の1。上限額35万円
B 解体工事費用の2分の1。上限額15万円
○担当部署
横須賀市役所都市部まちなみ景観課
【神奈川県厚木市の補助金等】
○補助金の名称
老朽空き家解体工事補助金
○補助の概要・目的
空き家放置による地域住民の生活環境への影響を防ぐため、空き家の解体や利活用の推進を目的に、市内の老朽化した住宅の解体費用を一部補助。
○補助の金額
解体工事費用が100万円以上の場合、50万円。
解体工事費用が100万円未満の場合は、解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)。
○担当部署
都市みらい部住宅課住宅政策係
千葉県内の補助金等
以下は54の自治体をもつ千葉県の一部の補助金等です。このほかの地域にも家屋解体に利用できる補助金等の制度をもつ自治体があるので、所有する家屋の制度を確認しましょう。
【千葉県千葉市の補助金等】
○補助金の名称
住宅除却補助事業
○補助の概要・目的
1981(昭和56)年5月31日以前の耐震基準によって設計・建設された住宅で、耐震診断の結果、倒壊する危険性の高いものについて、その住宅すべてを解体して除却する。
○補助の金額
工事費の23%。上限額20万円。
密集住宅市街地の場合は上限額30万円。
○担当部署
千葉市建築指導課
【千葉県木更津市の補助金等】
○補助金の名称
空き家除却工事補助制度
○補助の概要・目的
適切に管理されていない空き家が市民生活に影響を及ぼしていることから、市民の生命、身体および財産を保護、生活環境の保全を目的に、放置しておくことで倒壊など著しく危険になる恐れのある空き家の解体工事の費用の一部を補助。
○補助の金額
対象経費の2分の1。上限額50万円。
○担当部署
都市整備部住宅課
【千葉県銚子市の補助金等】
○補助金の名称
銚子市危険空家等除却事業補助金
○補助の概要・目的
そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがあり、利活用が難しい空き家の除却費用の一部を補助。
○補助の金額
対象経費の5分の4以内。上限額100万円。
○担当部署
都市整備課都市整備室空き家対策班
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事業務を展開しているマトイです。補助金等を含めた皆様の疑問点について、パートナーとしてのスタンスで皆様と一緒に向き合い解決しています。どうぞお気軽にお声掛けください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
補助金等の目的
所有している家屋等を解体しようとする場合、自治体に補助金制度があるととても助かります。しかし、なぜ解体工事に補助金等が出るのでしょうか?
補助金等の目的
さまざまな建築物や設備、そして自然、植栽などによって街とそこの環境が形成されています。そのため、その状態の良し悪しによって街の景観や防犯をはじめとした生活環境に大きな影響を受けることになります。
その1つが空き家問題です。管理されないまま空き家=管理不全空き家や特定空き家のようなものが増えることで、ゴミの不法投棄や獣などの住み着きによる不衛生、建物の老朽化に伴う倒壊リスク、不法侵入などによる犯罪の発生、そして街の景観の悪化等々が起こりえます。
そしてこれらは、すべてそこに暮らす人たちの安心・安全を脅かすものとなるのです。そのため、行政として人々にとって暮らしやすい街とするための方策の1つとして、補助金制度を整えています。
補助金と助成金の違い
このコラム内では「補助金等」と表記していますが、これは補助金と助成金の両方を含めての表記ととらえてください。
しかし、インターネットなどでさまざまな情報をあたっていると「補助金」「助成金」といった言葉が出てきて、「いったい、この違いは何?」と思うかもしれませんね。そこで、この違いをはっきり知っておきましょう。違いは次の点にあります。
○補助金
・国や自治体の政策目標に沿った事業者や個人の取り組みをサポートするため、その資金の一部を給付。
・返済の必要はない。
・申請要件の審査が必要。
○助成金
・研究や事業の支援を目的に支給。
・返済の必要はない。
・要件を満たしていれば必ず支給される。
補助金や助成金について、こちらのコラムで違いをはじめ建て替えなどの際の補助金等について解説していますので、ご覧ください。
建物解体に使える補助金の種類
冒頭に紹介した家屋解体に関するいくつかの自治体の補助金等を見てわかるかと思いますが、家屋の解体に活用できる補助金等の種類は、おおよそ次の3種類に分かれます。
解体補助金
老朽化した建物や倒壊の恐れがある建物の解体費用を補助するもので、「老朽建物解体補助金」ともいわれます。
建て替え工事助成金
家屋を解体撤去後に新築する「建て替えが前提」となります。
空き家対策補助金
空き家であることが前提条件となるものです。長期間、空き家のまま放置されている家屋の解体を促し、地域の活性化や防災対策を促します。
補助金等の情報収集から工事着工までに施主として行うべきことなどをまとめてあります。こちらも、どうぞお読みください。
補助金等に関する情報収集のポイント
補助金等を積極的に活用したほうがいいことはわかっていても、なかなか情報を見つけられない、という方もいらっしゃるでしょう。そこで、補助金等の情報収集のポイントを説明します。
自治体の公式ウェブサイトをチェック。
税金を財源にしている自治体による補助金等は、その自治体の公式ウェブサイトに掲載されます。
どのような補助金等があるか、その金額はどのくらいか、申請の手続き方法、そして申請期間や申請要件などを確認しましょう。
また、補助金等のなかには予算を限定しているものもあります。その場合、予算に達したら当初示されていた申請期間よりも早く締め切ります。こういった情報もウェブサイトに掲載されますので、頻繁にチェックするようにしましょう。
自治体の窓口を訪ねたり、電話で問い合わせたりする。
ウェブサイトを見ただけでは分からないことがあったり、探しきれない情報があったりします。その場合は、電話で問い合わせることで確認できます。
また直接、自治体の担当窓口を訪ねることで、ウェブサイトだけでは得られない情報やそれぞれの事情に合わせて必要な情報を得ることができます。
地域の広報誌やニュースレターなどにも目を配る。
自治体から配布される地域の広報誌やニュースレターも重要な情報源です。これらにも補助金や助成金に関する情報が掲載されますので、目を通すようにしましょう。
インターネット検索で広く情報を得る。
インターネット検索も補助金等の情報収集に役立ちます。
「解体工事」「除却」「〇〇県△△市(解体する建物が所在する地域)」「補助金」「助成金」などのキーワードを入力し、出てきた情報から知りたい情報をチェックします。
しかし、それだけを鵜呑みにはしないようにしましょう。あくまでの自治体の公式の情報を基に判断することが大切です。
補助金の申請・受給のための条件
家屋の解体に際して補助金等を利用するにあたっては、まず申請をし、審査を受けることになります。そのためには、クリアすべき要件がいろいろあります。それらは自治体や利用したい補助金等によって異なりますが、共通するものもあります。
対象物件としての条件
その建物が申請可能な対象物件であるためには、一般的に次のような共通条件があります。
・解体する建物の所在地と補助金制度等が同じ自治体。
・建物に顕著な老朽化がみられ、倒壊の危険性がある。
・長期間使用されていない空き家(通常1年以上)である。
・基礎部分に亀裂やゆがみなどが生じていて安全上に大きな問題を抱えている。
・自治体の審査によって解体の必要性が認められている。
税金を滞納していない。
補助金等の財源は税金です。そのため、補助金を申請するにあたっては、各種税金を滞納していないことが、申請者に求められる大きな条件になります。
そのほかに申請者に求められる条件には、次のようなものがあります。
・解体する建物の所有者である。
・相続した建物などで所有者が複数名存在する場合は、所有者全員の同意が必要。
・税金滞納のほかに反社会的な関係性がない。
過去に同じ種類の補助金の需給を受けていない。
申請者が以前に同様の補助金の受給を受けている場合は、一般的には新たな申請は認められません。
補助金等を活用して家屋解体を行う際の注意点。
補助金等を活用して家屋解体を行う際には、次の点に注意することが大切です。
補助金申請は業者決定より前に!
補助金等の申請は、家の解体を決めた段階で、業者を決定する前に行います。
補助金等の申請の条件の中なかには、同じ自治体内の業者や認定業者に依頼するといったものがある自治体もあります。その場合、業者の決定を先にしてしまうと申請できなくなったり、業者にキャンセルして違約金が発生したり、それまでの業者選定にかかった労力が無駄になる可能性があります。
まずは補助金申請の情報収集や申請手続きを先に始めてください。
マトイでは、自治体の補助金等の情報を把握したうえで、検討中の方からのお声掛けをいただいた際に、この点についてもお話をしています。そのうえで補助金申請と弊社との契約時期のタイミングを計りながら、全体のスケジュールを組むことも可能です。どうぞ安心してお声掛けください。
申請準備は時間の余裕をもって。
補助金の申請にはさまざまな書類を集め、書類に必要事項を記入するなどのため、申請に至るまでの時間がかかります。間違いや不足書類がないように、時間に余裕をもって申請しましょう。
申請をしても審査結果はすぐには出ない。
補助金等の申請から審査結果が出るまでの期間は、およそ1か月から数か月かかるといわれています。この期間は自治体によって異なります。申請時に、担当窓口の方に審査結果が出るまでのおおよその期間を聞いておくと、その後の計画が立てやすくなります。
補助金等が支給されるのは、解体工事終了後
補助金が支給されるまでには、おおよそ次のような流れになります。
補助金の申請➡審査結果➡解体工事開始➡工事完了➡補助金等交付
この一連の流れのなかで、工事が完了したら「工事完了報告書」を自治体に提出し、その内容を自治体が確認後に補助金等が交付されます。
工事完了報告書を提出してから補助金が交付されるまでは数週間から数か月かかるといわれ、自治体によって異なります。工事完了報告書の提出の際に、補助金等が交付されるまでどのくらいの期間がかかるのか聞いておきましょう。
何事にも計画は大事。しっかりした計画を立てるためにも、その流れの把握が必要です。こちらのコラムでは、解体工事全体の流れを説明しています。申請の流れと併せて、ご覧ください。
まとめ
家屋の解体工事に補助金等を利用することで、上限額があるものの数十万円から費用負担を軽くすることができます。ぜひ活用したいものです。
しかし、ここまでに説明したように、補助金等の活用にはさまざまな条件が伴います。また、解体工事が完了して一定期間おいてから交付されることから、施主様はそれまでの間の資金繰りを補助金に関係なく進めなくてはなりません。そのご負担は大きいですね。
そのため解体工事の着工から完了までさまざまなことを検討し、調整する必要があります。そんなとき、私たち業者をパートナーとしてご利用ください。
マトイでは「よく働くマトイ!」を合言葉に、施主様を力強くサポートしていくことをモットーにしています。東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で解体工事をお考えの方々はどうぞお気軽にお声をかけてください。解体工事はもちろんのこと、不用品の処分や残置物の取り扱いなど解体工事に付随したことも含めて、細かく皆様の計画をサポートしていきます! 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の解体工事は、どうぞマトイにお任せください!!
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
2025年最新! 建物の解体費用を徹底説明!
Next
内装解体を考え始めたら~単価や工法、手順を細かく説明





