老朽化や災害後、半壊した家は解体すべき? 判断基準と補助金の基礎知識
かいたいコラム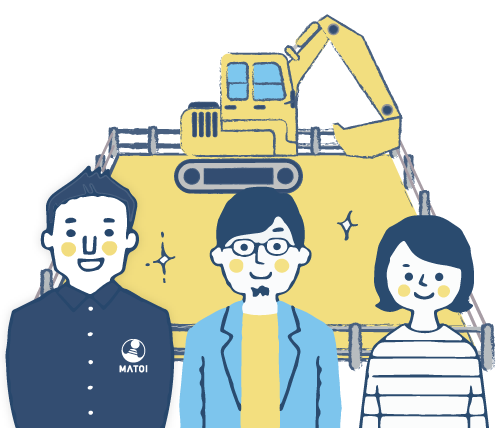
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
大災害が続いているなか、皆さんそれぞれが災害への備えを考えていることでしょう。その1つに、「もしも生活の拠点である自宅が損壊したら……」といったときの対応もあると思います。
所有する家屋等が損壊するのは、災害時だけではありません。居住している家屋や所有している空き家の老朽化が進むなかで、損壊することもありますね。
今回は老朽化や災害によって家屋が損壊した場合の対応やその判断基準、補助金等の利用について知っておきたい基礎知識をまとめました。
活用しないまま所有している空き家はありませんか?
人が住まない空き家は、老朽化がどんどん進みます。半壊・倒壊する前の対処をお勧めします。マトイでは、無料ご相談・無料お見積りで、空き家所有者をはじめとした方々のご相談に対応しております。お気軽にご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
老朽化やり災による半壊家屋の問題点は?
建物が一部損壊したり、倒壊したりするのは災害以外のことでも起こりえます。
それは冒頭に挙げたように、老朽化が進んだ場合にも起こりえることです。
完全に倒壊していれば、対応は解体撤去して建て替えたり、別の場所に新築したり、もしくは別の建物に引っ越すように、対応の選択肢は限られます。しかし、一部損壊や半壊の場合は、その判断が難しくなります。
適切な対策を検討するためには、まず半壊した状態の建物にどのような問題点が潜んでいるかを、明確に把握することが大切です。
半壊家屋の問題点には、次のようなものが挙げられます。
○安全性が不確実
一見した様子は一部損壊であっても、建物の構造が損傷を受けている可能性があります。それによって倒壊の危険性があったり、強風や地震によってさらに損傷部分が拡大したりする可能性があります。それによって家屋の安全性は大きく損なわれます。
○生活環境の悪化
損壊の程度がさほど大きなものでなかったとしても、生活環境に大きな影響を与えます。例えば屋根や壁の一部が破損していると、そこから雨漏りがしたり、害虫などが侵入したり、腐敗した木材や壁材などにカビや虫がわいたりして、住環境を著しく悪化させます。
○修繕や解体費用の負担
前述のように、損壊した部分を放置しておくとその建物の痛みは激しくなります。そこで可能な限り速やかに修理をする必要があるのですが、その費用が高額になることが多く、修理する人の経済的な負担が大きくなります。
○複雑な行政手続きの負担
建物の損壊した部分の経済的負担を軽減したり、公費での解体撤去を希望する場合、補助金や保険金をはじめとした公的な支援を受ける方法があります。しかし、その手続きは複雑なことが多く、また必要な書類をそろえる必要があり、申請手続きに労力を要します。
○資産価値の低下
適切な処置を行わないまま損壊した建物を放置していると、その土地や建物の価値は低下し、売却が難しくなります。
半壊家屋対処の責任者は?
家屋が損壊・倒壊した場合、その対処はだれの責任において行うべきでしょうか?
その損壊や倒壊の原因によって責任者は異なりますが、修繕や解体撤去など何らかの対処に向けての行動は、まず建物の所有者が行うことになります。この点において、“責任者は所有者” ということになるでしょう。
老朽化や被災で家が半壊。どのように対処する?
では自宅が老朽化や災害によって半壊状態になった場合、行政への相談、業者への依頼など具体的な対処をどのように行っていったらいいでしょうか。
対処の流れ
老朽化や災害時に被災した家屋の対処は、隠れた部分にもダメージが及んでいることが考えられるため慎重な対処が必要です。その流れは一般的に次のステップで進めます。
ステップ1 現状の確認
家屋の安全性と損壊の状態を確認し、今後の利用が可能かどうかをわかる範囲で調べます。(ご自身で状況を確認する際のポイントについては、次項で説明します)
ステップ2 専門家の意見を求める
建築士や施工業者にも依頼し、修理の必要性、修理可能な程度の損壊か否かを診断してもらいます。
状況に応じて、自治体や防災関連の機関にも相談しましょう。
ステップ3 活用できる保険金や補助金を確認
加入している損害保険、火災保険、地震保険などが適用されるか、保険会社に連絡を取ります。それとともに、家屋が所在する自治体の被災者支援制度や補助金制度についても確認し、活用できるか否かを調べましょう。
ステップ4 修繕または解体するかを選択
専門家の診断を受けて修繕もしくは解体するかを決定し、その準備を開始します。
修繕および解体のいずれの場合も業者から見積りをとり、予算や工期等のすり合わせをしたうえで施工業者を決定します。そこから工事に向けて必要な届け出や準備を進めます。
ステップ5 近隣との調整
工事の具体的な計画が決定したら、 近隣住民へ工事内容および周辺環境や安全面への配慮を事前に説明し、協力に向けての挨拶を行います。
併行して工事に伴い、自治体や関係機関への必要な届け出を行います。
ステップ6 今後の住まいの検討
修繕・解体に当たって、修繕中や解体撤去後に自分たちが住み続けるか、売却するか、それとも賃貸物件として活用するかなどについて検討します。これについては、ステップの初期段階から検討を重ねる必要があります。
状況の違いはあっても、解体工事の流れに大きな違いはありません。こちらのコラムでは木造家屋の解体工事の流れについて説明しています。併せて参考になさってください。
損壊の程度と判断基準
家屋の対処の選択は、その損壊の程度によっても異なります。
インターネット上で公開されている内閣府の「災害の被害認定基準」によると、損壊の程度は次のような基準で判定されます。
■被害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める被害の割合)
| 全 壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
| 半 壊 | 20%以上30%未満 |
| 準 半 壊 | 10%以上20%未満 |
| 一部損壊 | 10%未満 |
※内閣府「防災情報のページ」より引用
被災状況の自己判定のポイント
【災害時の復旧活動の流れ】
災害時の復旧活動は、次の流れで進められます。
罹災状況調査等による被災状況の評価➡罹災証明書発行➡行政を含めた復旧支援
罹災状況の具体的な評価基準は地震や水害といった災害によって異なります。その災害に応じた調査基準に基づいた調査が進められ、罹災証明書の発行、そして各種支援へと進んでいきます。
【できるだけ早い状況把握と支援に向けて】
災害時、居住している家屋が損壊していたら、できるだけで早期に対応を進めたいと思うことでしょう。そういう思いに対し、自治体では現地調査を省略して被害箇所を写真撮影して、それによって罹災証明書を発行するといった体制をとるところもあります。これによって比較的早期に復旧に向けて取り組めるようになります。
ただ復旧に向けて、罹災状況を評価するときの難しい点の1つに、準半壊や一部損壊の判断があります。どの程度までが一部損壊で、どこからが半壊になるのか、一般の人が判断しかねます。
準半壊や一部損壊の見極めが難しかったとしても、まずは画像とメモなどで状況の記録をとって自治体に相談することが大切です。
【状況をチェックする際のポイント】
状況チェックの際は、次の点がポイントになります。
○建物の構造的な損傷
・壁や柱に亀裂が入っていないか?
・屋根のゆがみや破損はないか?
・床の傾きや沈み込みはないか?歩いたときに違和感があると、基礎が損傷している可能性がある。
○外観の変化
・ドアや窓に開閉のしにくさはないか?
・外壁に剥がれやひび割れはないか?
・屋根材や雨どいに破損はないか?
○内部に異常はみられないか?
・天井や壁に雨漏りの兆候であるシミができていないか?
・強風時や歩行時に軋むような異音はしないか?
・電気、ガス、水道に問題はみられないか?
○周囲の状況
・隣家や道路との間に、ズレはないか?このズレは地盤の変化の可能性を示す。
・地面に陥没やヒビ割れがあるか?
以上の点を確認し、認められたら該当箇所の撮影をします。そして自治体の担当窓口や構造診断士・建築士などの専門家に相談し、必要に応じて専門家に正確な評価をしてもらい、今後の対処を相談・検討します。
災害時、確認した該当箇所を撮影した画像等をもって自治体窓口に行くことで、り災証明書を迅速に発行してもらえる可能性があります。それによってその後の対処もスムーズに進められます。
解体するべきか否かの判断のポイント
家屋の損壊の程度にもよりますが、修繕するか解体するかの判断が必要になります。その検討と判断では、次の3点ポイントになります。
ポイント1 修理費用が支払い可能な範囲であれば修繕を検討。
ポイント2 安全面に大きな問題があり、長期的に住むことが難しい場合は解体を選択。
ポイント3 上記2ポイントと併せて、資産価値や再活用の可能性も考慮する。
これらのポイントに沿った検討をする際、具体的な点として次のことを見極めながら、慎重に判断してください。
○構造面の安全性は保たれるか?
・壁や柱が著しく損傷している場合、倒壊の危険性がある。
・家全体が傾いていたり、沈下したりしている場合、基礎が損傷している可能性がある。
・損壊以前の建物が過去の耐震基準に適応していない場合、さらなる耐震性能の低下が予測され、大幅改修が必要になる。
○修繕の可能性はあるか?
・建て替えるよりも修繕に多額の費用がかかる。
・修繕後も頻繁なメンテナンスが必要となり、長期使用が困難。
・家族構成やライフスタイルの変化に伴うバリアフリーや高齢者向け対応が難しい。
○法規制と行政対応に問題はないか?
・以前から倒壊の恐れがある危険建物として行政指導を受けている。
・もともと建築基準法に適合していない建物。
・補助金や解体費用の支援制度の活用が可能。
○経済的・資産価値は保たれるか?
・解体したほうが、駐車場や賃貸物件の新築、もしくは土地売却などで活用できる。
・固定資産税や修繕費など、維持管理費が高額。
・築年数や環境によって市場価値が低下。
これらを自分だけで見極めて結論を出すことが難しい場合は、建築士や不動産専門家などに相談すると、より適切な判断ができます。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で家屋解体事業を展開しているマトイでは、お見積りはもちろん、解体工事検討段階からのさまざまな疑問やご相談にも無料で対応しております。お気軽にご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
解体に向けて利用可能な公費解体や補助金
家屋の解体費用は多くの場合、高額になります。何もない平穏なときに解体工事をするにも経済的に大変であるのに、災害によってさまざまな負担を抱えているなかでは、なおさらです。
そんなときに備えて知っておきたいことが、行政による経済的支援です。災害によって家屋が損壊した場合に活用できる公費解体や自費解体の制度、それ以外のときに利用可能な各種補助金制度があります。
公費解体
公費解体は、被災した家屋の所有者に代わって自治体が建物の解体撤去を行います。
これは解体業者との連携も含めたすべてを公費によって自治体主導で行われるため、所有者の負担は少ないです。しかし、申請までの負担が大きく、解体工事着工までに時間がかかります。
自費解体
自費解体は自費解体費用償還制度と呼ばれ、所有者自身が解体業者と契約し、かかった費用を後に自治体に償還申請を行います。
ただし、建物が全壊もしくは半壊していることを証明する解体工事前・解体工事中・解体工事後の状況を記録した写真や業者との契約書や領収書などが必要です。
自費解体では早期に解体作業に着手できます。一方で所有者が費用を負担しますが、それは申請要件を満たしていれば後に自治体から償還されます。
公費解体や自費解体については、こちらのコラムで詳しく説明しています。こちらも併せてお読みください。
公費解体や自費解体が利用できないケース
公費解体や自費解体の要件は自治体によって異なりますが、利用できないケースとしておおむね次のようなことが挙がります。
・適用されるのは被災判定が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のもので、半壊未満のものは対象外となる。
・各自治体によって補助の基準額があり、その範囲を超える費用。
・倒壊の恐れがない庭木、庭石、ブロック塀、擁壁等の撤去。
・改修や補修による廃棄物の撤去。
・被災証明がない空き家。
・解体後の整地費用。
・自費解体において、解体業者との契約前に市町村へ相談しなかった場合。
老朽家屋に対する補助金制度
災害による損壊による家屋解体のほか、老朽化のために家屋を解体する場合は公費解体や自費解体は適用されません。しかし、自治体のなかには次に挙げるような補助金や助成金制度によって、その支援を行っているところがあります。
・老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽化して倒壊の恐れがある空き家の解体費用の一部を補助する制度。
・市町村の空き家対策補助金
空き家の解体を促進するための補助金。
・密集市街地の危険建物除去補助
木造住宅密集地域などの防災対策として、対象地域にある老朽化した建物の解体費用を補助する制度。
以上の補助金制度は、制度の有無や補助金額・補助上限額、および申請要件などが自治体によって異なります。
そのため、利用の検討段階から対象の家屋が所在する自治体にどのような制度があるか、その補助内容や申請要件等の確認が必要です。
こちらのコラムでは、東京都の家屋解体の補助金・助成金について説明しています。こちらも参考になさってください。
各種補助金等、申請時の留意点
老朽化が進んだ家屋、り災によって半壊以上の損壊を受けた家屋を解体する場合、これまで説明してきた「公費解体」、「自費解体」、「その他の家屋解体補助金」の制度を活用することが、経済的な負担の軽減につながります。
そこで、これらを利用する際の留意点を説明します。
公費解体利用時の留意点
・罹災証明書の発行を受けて、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の判定を受けていること。
・必要書類として次のものを整えておく。
申請書、罹災証明書、建物の所有者が申請者と異なる場合は所有者の同意書、登記事項照明など。
・申請期限を確認。申請期限は自治体ごとに異なる。
・解体業者は自治体が指定した業者を利用。
自費解体利用時の留意点
・自費解体で家屋解体を進める場合は、業者との契約以前に自治体担当窓口に事前相談をしておく。相談時には、見積り書、現場の写真、配置図などを準備。
・償還される費用は、おおむね公費解体と同様の基準で算定。
・解体完了後、マニフェスト伝票、現場写真、解体費用内訳書等を提出。
・償還金の振込先は申請者本人名義であることを確認。
その他の家屋解体補助金利用時の留意点
・解体業者と契約の前に自治体の担当窓口に事前相談を行う。
・必要書類を確認し、それらを準備。
・市税や国民健康保険税などの滞納がないこと。滞納があると、補助金の対象外になる場合がある。
・自治体ごとに申請期限や補助金の予算枠が決められている。申請件数等が予算に達した場合は、申請期限前であっても、申請受付を終了することがある。
・自治体によって業者の指定条件や業者が指定される場合がある。
まとめ
「家屋の損壊」は、そこで暮らす人の生活や所有する人にとって大問題です。
また、その対処には今回説明しているように、いくつかのポイントがあります。そのなかで重要になってくるのは、相談機能や補助金制度など行政の支援を活用することです。
そのためには、日常から行政の支援体制について知っておくこと、そしてその活用が必要な事態が起こったときには、最初に行政の窓口とコンタクトをとることが重要です。
例えば、解体に当たって解体業者との契約をはじめに進めてしまうことで、補助金制度等の活用が難しくなるようなことも起こりえます。まずは行政の窓口と連絡を取りながら、対処を進めることが一番のポイントといえます。
マトイでは今回のテーマに挙がったような老朽化による半壊家屋や被災による家屋の解体も含め、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体事業を展開しています。それとともに、補助金の利用や残置物・不用品処分など解体工事に伴うさまざまな相談にも対応しています。
いざというときや、ライフスタイルの変化に伴う住まいの解体やリフォームなどを計画の際にも、どうぞマトイをご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
解体工事の仮囲い基準ガイド~安全対策と近隣トラブルを防ぐ方法
Next
取り壊し費用はいくらかかる? 建物付き土地の売却前に知っておきたい基礎知識





