納屋解体の費用相場はいくら? 費用を抑えるコツ
かいたいコラム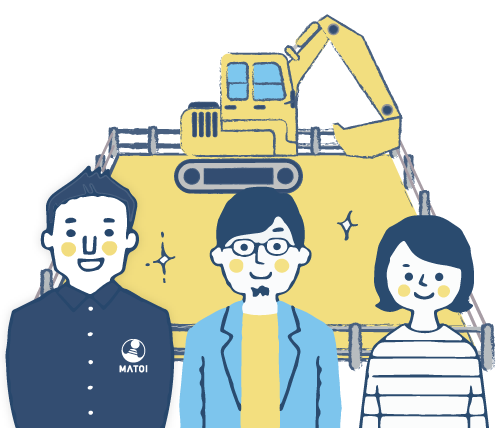
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
所有地の隅に、使わないままの小屋がある家は意外と多いようです。
「あの小屋は何に使っていたんだろう?」、「今は使っていないけれど、防犯面からも処分したほうがいいかも」などと考えているものの、なかなか実行に移せない方もいるようです。
そのような建物の1つに「納屋」があります。今回は、納屋の解体についてみていきます。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で、小さな物置から一般家屋、そしてオフィスビルのような大型の建築物まで、さまざまな建物の解体工事を行っています。
建物の解体工事やリフォーム工事、それらに伴うご相談等にお応えしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
納屋の定義と倉庫や物置との違い
納屋と似たものに、倉庫や物置があります。これらは日常の場面では、厳密に使い分けることはあまり見られず、どれも物を保管することを目的とした建物です。
しかし、それぞれを詳しくみると、納屋・物置・倉庫のそれぞれには違いがあります。
納屋とは
納屋は農機具の格納、家畜の飼料の保管、収穫物の乾燥や乾燥させた収穫物を保管するなど、農業用の保管を目的とした小屋です。そのため、多くの場合、農地のそばにあります。
昔からあるもので、木造のもののほかプレハブなどのものもあります。
物置とは
物置には、DIYなどに使う工具・タイヤのスペア・除雪道具・日常的には使わない季節用品などを保管しておきます。そのため、家の敷地の隅や裏庭、ベランダなどに設置されます。
小型かつ簡易的なプレハブやスチール製のものが主流です。
倉庫とは
倉庫は、商品や資材などを大量に保管するものです。それだけに、倉庫のなかには、フォークリフトが中に入って作業ができるほどの広さや、床から天井までの高さがある大型のものもあります。また、堅牢な造りで耐火性や防犯性も重視されます。
納屋や物置が個人のためのものであるのに対し、倉庫は企業や事業者が商品・資材管理をするために用いる傾向にあります。
日常では、物置も倉庫も納屋も、自宅の庭の片隅や畑のそばに立っている様子を見ると、「小屋」の一言で済ませがちなほど、使い分けが曖昧です。その「小屋」の解体について、こちらのコラムで説明しています。納屋の解体の参考になさってください。
納屋を解体する際の留意点
農機具や収穫物の保管等に使用されている、もしくは使用されていた納屋を解体する場合、どのような点に留意するべきでしょうか。
さほど大きくもなく、しかも長年使われていない納屋は、そのまま解体してしまいがちですが、事前にチェックしておくべき点があります。
害虫の有無を確認
収穫物や農機などを保管し、農地内もしくは農地付近に建っている納屋には、柱を侵食するシロアリのほか、貯蔵している穀物等に巣食う害虫や湿気やカビなどが発生する場所を好む害虫などが存在している可能性があります。ネズミも見逃せません。
そのため、解体する前に害虫やネズミなどがいないか否かの事前調査と駆除処理が必要です。それをしないまま解体工事等を行うと、逃げ出した害虫等が近隣に侵入して迷惑をかけかねません。
また、シロアリの被害を受けていた場合、その部分が脆弱になっていることから、解体作業時に崩壊のリスクがあります。この点も確認を行い、安全な工事を進めます。
文化財保護条例抵触の有無
築年数が古い納屋のなかには、歴史的建造物になりうるものがあります。その場合、解体によって文化財保護条例などに抵触しないかどうかを確認してから解体工事に移ることが大切です。
また、納屋の梁や柱などは、状態によって古材として買い取ってもらうことができます。そのため、古いもので柱等がしっかりしている場合、解体工事前に査定してもらうことをお勧めします。
納屋解体の流れと期間
納屋の解体は次のような流れで進めていきます。またそれぞれの段階にかかる期間も示しますが、これについては1つの目安としてください。具体的には大きさや構造によって異なります。
こちらのコラムでは、一般的な解体工事の流れや作業内容について説明しています。併せてお読みください。
現地調査と構造確認
最初に、解体工事を依頼する候補となる業者を数社選び、それぞれに現地調査を実施してもらったうえで、見積り書を出してもらいます。
この段階では、次のことを確認します。
〇建物の構造(木造・鉄骨造など)、築年数、面積など。
〇床面積が80㎡以上の場合は、解体工事着工前にアスベストの事前調査を実施。
〇農業用か住宅附属かといった登記状況を確認。
〇所要期間の目安:1~7日
(見積りを依頼するための複数の業者の選定にかかる期間は、施主様によって異なるため、上記の期間に含めていません)
解体業者の選定と本見積りの取得
複数の業者から見積りを取得したら、それぞれの内容に比較とともに、見積り依頼等を通した業者の印象や対応の良し悪しなどから、工事を依頼する業者を決定します。そして必要に応じて、本見積りを取得します。
なお、マトイでは最初の段階の見積りでしっかり現地調査を行ったうえでの本見積りをご提出します。またその段階で、追加工事発生の可能性やその場合の対応などについてもご説明します。
そのため、マトイを選んでいただけたら、すぐに工事準備および工事着工に着手できます。これはマトイを選んでいただく施主様にとって大きなメリットにつながります。
〇見積りの比較検討では、坪単価や付帯費用、廃材処理費、足場・養生の設置費用など具体的な項目内容および追加工事発生時の対応等も含めて確認。
〇古材の再利用や買取の可否も併せて確認すると、コスト削減が可能に。
〇所要期間の目安:7日
解体工事の見積りでは、概算見積りと本見積りがあります。こちらのコラムで、説明していますので、参考になさってください。
解体工事の契約を交わし、着工への準備
解体工事を依頼する業者を決定したら、次のような流れで着工へと進めます。
〇工期、費用、廃材処理方法、近隣への対応などを再確認。
〇近隣の住民への挨拶と説明。
〇床面積80㎡以上の納屋の場合は、アスベスト事前調査を実施。
〇納屋の状況に応じて、害虫駆除処理を実施。
〇納屋内にある不用品等を処理・処分。
〇建築リサイクル法などに関する諸手続き。
〇足場を取り付け養生シートを設置。
〇所要期間の目安:7~10日
工事着工~完了
解体作業は、以下の流れで進めます。
屋根や壁材を手作業で撤去
↓
重機を用いて構造体を解体
↓
基礎を撤去
〇所要期間の目安:3~7日
廃材処理・整地
基礎を撤去したら、残っている廃材を分別して処理場へと搬出。そして整地します。
〇所要期間の目安:1~2日
廃材をはじめとした廃棄物の処分について、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞこちらもお読みください。
建物滅失登記等の手続き
納屋の解体工事がすべて終了したら、建物滅失登記を納屋が所在する法務局で行います。また、納屋を解体撤去後の土地を農地転用したり、建て替えたりする予定がある場合は、それらに応じた申請が別途、必要になります。
〇所要期間の目安:建物滅失登記は解体完了日から1か月以内に行う。
建物の解体工事には付き物ともいえる建物滅失登記について、こちらのコラムで説明しています。併せてお読みください。
納屋の解体費用
納屋の解体費用は、木造の場合で一般的に2万円~となりますが、構造・立地条件・築年数によっても変わります。
解体費用は坪単価を基にして計算します。
その坪単価について、こちらのコラムで詳しく説明していますので、こちらもお読みください。
納屋の解体費用と、一般的建物の解体費用の違い
納屋の解体費用は、前項で示したように一般的な木造家屋よりも安い価格になります。また一般的な建物と比較すると、次のようになります。
| 建物の種別 | 坪単価の目安 |
| 納屋(木造) | 約2万円~ |
| 木造住宅 | 約5万円~ |
| 鉄骨造住宅 | 約7万円~ |
| 鉄筋コンクリート造住宅 | 約10万円~ |
納屋の解体費用が安い理由
上の表を見てわかるように、納屋の解体費用は他の場合と比較するとリーズナブルです。それは次の理由からです。
・内装が少ない
一般的な家屋と比較して、断熱材・配管・電気設備等が少ないため、分別や処理コストが低くなる。
・簡素な構造が多い
間取りが少ない、もしくは1室だけの構造で、トタン屋根や木造柱だけのシンプルな構造のものが多い。
・再利用可能な古材が多い
買取やリサイクル等で処分費用がかからない。場合によっては費用を一部回収できることもある。
ただし、場合によっては害虫駆除処理やアスベスト事前調査およびアスベスト処理に追加費用が発生することがあります。
費用を変動させる要因
一般的家屋よりも解体費用が安い傾向にある納屋ですが、その費用を変動させてしまう要因として次のようなものがあります。
建物の構造や老朽化の程度
納屋のなかには、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などのものもあります。そうなると、解体費用の坪単価は高くなります。
また老朽化が激しいものだと、柱が腐食しているなどで崩落の危険性があるため、慎重な作業で時間を要したり、その分の人手が必要になったりして、費用がかさみます。
残置物の量や種類
残置物として家財道具、農具、穀物、段ボール等が大量に残っていると、処分費用が増加します。
また農薬や塗料など特別な処理が必要なものが残っていると、別の費用が発生します。
解体工事を始める前に、建物内にある残置物を処分することが必要です。こちらのコラムで、解体工事を前にどのように室内にあるものを処分するかを取り上げています。どうぞお読みください。
立地条件
狭い場所、傾斜地、山間部などになると、重機の搬入や工事車両の進入が難しく、追加費用が発生する場合があります。
また都市部では、騒音や振動対策とともにその費用が増加する可能性があります。
アスベストや害虫などの有無
現在、床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、アスベストの事前調査が必要です。この調査でアスベスト含有建材を使用している場合は、そのレベルに応じた方法で撤去することが義務付けられています。この事前調査や撤去に費用が発生します。
また害虫がいる場合も、解体工事前にその駆除処理を行います。
業者
解体工事費用に一律の基準はなく、業者、地域、立地条件、建物の構造や広さなどによっても異なります。
とくに業者によって料金体系やサービス内容が異なるため、見積りが届いたら、その項目内容に至るまで細かくチャックする必要があります。
費用を抑える方法
できれば解体費用を抑えたいとは、施主の立場になる方々の多くが考えることでしょう。そのためのポイントを以下にご紹介します。
複数の業者から見積りをとる
解体費用は業者によっても、大きな違いがあります。そのため、複数の業者に無料見積りを依頼することで、その地域でのおおよその相場や業者による費用の違いを知ることができます。
また、そのためのやり取りを通して、業者の対応の良し悪しなどから誠実に仕事に臨んでいる業者か否かも判断できます。
残置物を事前に自分たちで処分する
解体工事の際の残置物は、産業廃棄物として処分されます。そして産業廃棄物は一般廃棄物よりも処分費用が高額になります。
できれば、納屋に残っているものはご自身で処分したほうが、処分費用を抑えられます。
自治体の補助金等を活用する
自治体のなかには、建物の解体工事に対して補助金や助成金制度を整えている場合があります。
最初に情報を確認し、自治体の窓口で解体する建物などを伝え、利用可能か否か、利用に当たっての注意点などを確認し、積極的に活用することで、解体費用による経済的負担を軽減できます。
納屋の解体に利用可能な東京都の補助金等
東京都では東京都内広域にわたる補助制度と、自治体による補助制度があります。そのなかで納屋の解体にも利用可能な補助金等の一部を紹介します。
東京都の広域補助制度
補助金名:東京都空き家家財整理・解体促進事業
対象となる建物:都内に所在する納屋を含む空き家。東京都空き家ワンストップ相談窓口に事前相談が必要。
助成内容:
・家財整理費用の2分の1(上限5万円)
・解体工事費用の2分の1(上限10万円)
東京都世田谷区の場合
補助金名:不燃化特区老朽建築物除却助成・建て替え助成。
対象となる建物:世田谷区内の不燃化特区に建つ、耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物、耐火または準耐火建築物でないもの。
助成内容:
・老朽建築物およびそれに付属する工作物の除却工事費、および除却後の敷地の整地費用。
・除却する老朽建築物の延床面積1㎡あたり27,000円を限度(千円未満切り捨て)とし、実工事費と限度額と比較して少ない方の額を助成。
東京都練馬区の場合
補助金名:アスベストの調査費用および除却工事費用の助成制度
対象となる建物:練馬区内に所在する民間の建築物。
助成内容:
・建物の吹付材にアスベストが含有されているかの調査費用。10万円を限度額として、調査費用の2分の1。
・延床面積1,000㎡未満の建築物の場合、除却工事費用の2分の1(限度額400万円)。
・延床面積1,000㎡以上の建築物の場合、除却工事費用の24分の19(限度額600万円)。
補助金の活用時のポイント
補助金等を活用する場合、次に挙げるようにいくつかのポイントを抑えておくことが必要です。
・解体工事を検討し始めた段階で、解体する建物が所在する自治体に対象となる補助金等の制度があるか、自治体のホームページや直接問い合わせるなどして確認してください。
・補助金等の申請は解体工事に着工してからでは、受け付けてもらえません。解体工事の検討を始めた段階で、制度の有無、申請方法などの確認、および自治体の担当窓口への相談をして、申請へと進めていきましょう。
・解体工事の補助金等の制度は空き家や住宅に対するものが主ですが、納屋でも登記している建物の用途によって申請が可能な場合があります。ホームページ等の情報に“納屋”という文言がなくても、自治体に直接問い合わせて確認することをお勧めします。
・自治体の補助金等は、税金が主な財源です。そのため税金の滞納があると申請を受け付けてもらないことがあります。
マトイでは皆様に補助金・助成金の活用をお勧めしています。そして、皆様が円滑に補助金等を活用できるよう、必要な情報を集めて全力でサポートしています。
マトイ助成金について
解体工事を考え始めたら、どうぞ、早めにマトイにご連絡ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
納屋をDIYで解体できるか?
納屋の解体をご検討中の方のなかには、DIYでの解体も考えている方もいらっしゃるでしょう。DIYでの解体も可能ではありますが、安全に解体するためには検討すべき点がいくつかあります。
DIYを趣味にしている方もたくさんいらっしゃいますが、それぞれの熟練度によってもケガなどの危険性は違ってきます。
こちらのコラムでは、「家を自分で解体できるか?」という点に焦点を当ててDIYについて説明しています。
こちらも併せてお読みください。
DIYによる解体が可能か否かの見極めポイント
DIYで解体する場合、安全性、法令、体力、廃材処理など検討すべきポイントがあります。
ポイント1:構造がシンプルであること。
木造、トタン屋根、基礎が浅い場合は、重機を使用する部分が少なく、基本的な工具で解体が可能。
ポイント2:築年数とアスベストの有無。
延床面積80㎡以上の建物の場合は、アスベストの事前調査とその結果報告が必要。また、2006年以前の建物はアスベストを使用している可能性が高い。
ポイント3:建設リサイクル法による届け出を行う。
延床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法によって届け出が必要。
ポイント4:ライフラインの有無。
電気、ガス、水道が通っている場合は停止手続きを行う。
ポイント5:廃材の処分。
自治体のルールに従って、分別・搬出する。
ポイント6:近隣への配慮。
解体工事によって騒音や粉じんが発生するため、近隣の住民へ事前の挨拶と説明を行う。
ポイント7:必要な工具類および装具を整える。
必要な工具類や装具は安全に解体工事を行うために欠かせない物で、DIYに取り掛かる前にしっかりと準備する。
DIYの流れと注意点
基本的には、DIYで解体するのと業者が解体するのとでは、解体の流れに大きな違いはありません。
ただし、DIYの場合は、一連の作業を1人、もしくは介助者を含めても2~3人で行うことが多いようです。
納屋をDIYで解体する流れ
DIYで解体をする場合、おもに次のような流れで進めます。
1. 屋内にあるものを外に搬出する。
納屋のなかに残っている不用品は、リサイクル業者への依頼も検討し、残ったものは地域の粗大ゴミ回収を利用して処分。
2. 屋根材を撤去する。
脚立やはしご等を使って納屋上部に上り、バールやハンマーで釘を抜きながら屋根材を慎重に剥がす。
3. 壁材を解体する。
のこぎりやバールで分割しながら、取り外していく。
4. 柱や梁を撤去する。
上から順に切断し、内側に倒すように作業を進める。
5. 基礎を撤去する。
コンクリートブロックの基礎の場合は、ハンマーで破砕しつつ撤去していく。土間コンクリートの場合もハンマーやバールを用いながら解体撤去していくが、かなり重労働になる。そのため、一般的には、土間コンクリートの場合は業者に解体依頼する。
6. 廃材を分別・搬出・処分する。
廃材は現場で分別した後、分別して自治体のゴミ回収を利用して廃棄するとともに、軽トラック等に積んで処理場へ運搬して処分する。
DIYで納屋を解体する際の注意点
〇安全を最優先に、ヘルメット・防塵マスク・ゴーグル・手袋・安全靴などの安全装備をしっかり整えましょう。
〇延床面積80㎡以上の場合は、専門業者にアスベスト事前調査を依頼し、アスベスト含有建材等を使用していないことを確認してから、DIYで解体工事を開始します。アスベスト含有建材等を使用している場合は、業者に依頼します。
〇屋根部分の解体など、高所作業や納屋の老朽化の程度によって倒壊の可能性もあります。介助者として協力者を加えて複数名での作業することで、事故やケガのリスクを減らせます。
〇DIYでの解体では、自治体の補助金制度が使えない場合があります。
DIYのメリットとデメリット
DIYで解体を行うには、メリットとともにデメリットもあります。DIYで解体するか、業者に依頼するかを選択するときの参考にしてください。
DIYで納屋を解体するメリット
DIYで解体するメリットには次のようなことがあります。
〇人件費や管理費、マージン等が省けて、解体費用を節約できる。
〇休日や空き時間等を使って、自分のペースで作業ができる。
〇建物の構造や古材の状態を自分で確認し、再利用可能なものを自分で選別・保存できる。
DIYで納屋を解体するデメリット
一方、デメリットには次のようなものがあります。
〇老朽化が進んだものは、予期していなかった崩落や落下物の危険性がある。
〇高所作業や電動工具の使用に際し、防護具や知識が必要。
〇アスベストの事前調査、産業廃棄物扱いの廃材処理等は、無資格者が実施することは法令違反になる。そのため専門業者に依頼する。また害虫駆除処理なども必要になり、自分だけで工事を完結することはできない。
〇電動ハンマー、バール、脚立、養生シートなど必要なものを揃えるのに、費用がかかる。
まとめ
納屋は構造がシンプルで、さほど大きなものでない場合は、ご自身で解体しようと思う方もいるでしょう。
しかし、古いものであればあるほど、解体時に予期しないところが崩壊するリスクやケガのリスクが高くなります。また、アスベストの事前調査のように、どうしても専門業者に任せなければならないことも。これらを合わせると、DIYで期待していたほどコストを抑えられない可能性も高いです。
プロの解体業者であれば、建設リサイクル法等の届け出から安全対策、廃材処理もきちんと対応し、スムーズに工事を進めます。
なおマトイでは、害虫処理をはじめとした解体工事に伴って発生する必要な対処については、安心して任せられる業者と連携を図りながら、工事を円滑に進めていきます。
そのため、施主様からは「結果的に手間が省けて、安心して工事を任せられて楽だった」と喜ばれています。
マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事を行っていますので、この地域で解体工事をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。「マトイに任せてよかった!」といっていただける仕事をいたします。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
解体工事の粉じんトラブルを防ぐ5つの対策方法~苦情を未然に防止!~
Next
土蔵の解体費用はなぜ高い? 構造・材質ごとの費用比較と注意点










