国土交通省からも補助金が! 空き家解体時の補助金は早い者勝ち‼
かいたいコラム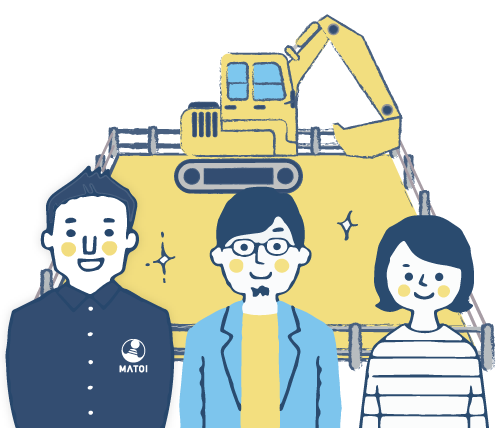
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
家の解体時に活用したいものの1つに補助金があります。
補助金の多くは自治体を通しての活用になりますが、そのなかには国の支援を受けているものも少なくはありません。今回はそうした国からの補助金となる国土交通省の「空家再生等推進事業」について、そしてこの事業から派生する自治体の補助金などについて説明します。
「国から自治体へ」と聞くと、空き家所有者は直接関係がないように感じるかもしれません。しかし、最終的には所有者へと流れるもの。ただし国も自治体も補助金には予算枠を限定しています。いうなれば補助金を受けるのは“早い者勝ち”。多くの場合、申請が予算に達したらその年度の支給は打ち切りとなります。補助金制度の内容や仕組みを理解して、積極的かつ早めに活用しましょう。
空き家の対処についてはいくつもの選択肢があり、迷うことも多くあります。そんなときはマトイにお気軽にご相談ください。ご相談者のご希望や空き家の状況などを併せて、よりよい選択を共に考えさせていただきます。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
ご存じですか? 国土交通省による「空家再生等推進事業」
自治体の補助金は、家屋を解体する際の経済的負担を軽減するためにぜひ活用したいものです。そして、この補助金の資金源の1つが、国土交通省の空家再生等推進事業による国から自治体への補助金です。
空き家対策は「空き家対策特別措置法」を根拠として進められています。こちらのコラムで同法律について、そして2023(令和5)年12月の改正内容等について説明しています。どうぞご覧ください。
「空家再生等推進事業」の概要
まず、家屋解体のための補助金の資金源の1つとなる国土交通省による「空家再生推進事業」について説明します。
【事業の目的】
空き家の増加によってその地域の居住環境に影響がある、地域の活性化の妨げとなる区域に対し、環境を整え、地域活動の活性化を図ります。
そのためには管理不全空家や特定空家のような不良住宅をはじめとした空き家を除却したり、そういった建築物を再活用したりすることが対策として必要になります。
それぞれの自治体が、地域内にあるそういった状態の区域の対策を積極に図るためには、プロジェクトを立ち上げて行います。が、それには資金が必要です。「空家再生推進事業」は、自治体が空き家の対策のためのプロジェクトを立ち上げる支援をする補助金を提供しています。
それによって得られた補助金を各自治体では、プロジェクトの立ち上げをはじめ空き家の修繕や改修、賃貸利用した後の家屋の管理費用などにも活用されることがあります。
空き家の解体を検討時に注目したい「除却事業タイプ」
この空家再生等推進事業は、「除却事業タイプ」と「活用事業タイプ」に分けられます。
除却事業タイプは、不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除去費用に対する補助を行うもので、居住環境の整備改善を図ることを目的としています。
一方、活用事業タイプは、空き家住宅や空き建築物の活用を進めることで、居住環境の整備改善を図ることを目的としています。
これ以降は除却事業タイプについて説明を進めます。
除却事業タイプによる事業内容
除却事業は老朽化して危険な不良住宅や空き家を撤去します。加えて、その跡地に小さな公園を整備したり、狭い道路に自動車や歩行者がすれ違うためのスペースを確保したりする用地として活用します。
除却事業タイプの対象施設
除却事業の対象となるのは、おもに次に挙げる3つです。
○不良住宅
空き家であるか、そうでないかに関係なく、老朽化に対して適切な修繕や管理がなされていない住宅や、構造的な欠陥など住む人やその周辺の人々などの健康や安全に支障を与える可能性が高い住宅。
○空き家住宅
居住する人がなく、使われていない住宅。
○空き建築物
人が住んでいない、もしくは使用されていない建物。空き家住宅は居住用の建物に限定されますが、空き建築物は商業用建物、工場、倉庫などさまざまな種類の建物を含みます。
除却事業タイプの助成対象費用
除却事業による助成費用は、次に説明するように対象施設や使用用途によって異なります。
○不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除却等に要する費用を助成します。
具体的には、除却工事費用については国と自治体によって助成することになります。その負担の割合は、国が5分の2、自治体が5分の2、民間が5分の1となります。
例えば除却工事費用が全額で200万円としたら、国が80万円、自治体が80万円、建物の所有者は40万円を負担することになります。このように実際に計算してみると、やはり補助金は積極的に活用したいですね。
しかし、補助金はどの自治体でも整備しているものでもなく、補助金制度があってもその内容は自治体によって異なります。そのため、家屋の解体を検討し始めたら、まず建物が所在する自治体において補助金制度があるか否かの確認が必要です。
知っておきたい国からの補助金が活用されるまでの仕組み
国から支給される空家再生等推進事業の補助金については一定の基準によるもののはず。それなのに自治体によって家屋解体等に関する補助金が支給されるところと、そういった補助金の制度がない自治体があるのはなぜなのでしょう?
一般的に国の補助金が自治体に支給されるには、次のような流れで行います。
① 予算計画・申請募集:年度ごとの国家予算に基づいて、関係省庁が予算計画を立てて補助金制度を調整。その後、補助金の申請募集を開始するとともに、補助金の目的や要件、申請手続きなどの募集要項を公表。
② 申請提出:自治体は募集要項を確認すると、必要な書類を整えて申請。
③ 審 査:国の関係機関によって自治体が提出した申請書類を審査。
④ 決定通知:審査を経て補助金の支給が決定すると、自治体に連絡。
⑤ 支 給:補助金が自治体に支給。
この流れを見てわかるように、自治体が国からの補助金を受けるためには申請をする必要があります。
しかし、なかには申請しない自治体もあります。それは、自治体の財政状況や予算配分、地域の状況やニーズ、さらに他に優先すべき事項があるなどの理由からです。
ここで取り上げている空家再生推進事業においても同じ理由から、自治体によって空き家対策における補助金制度が設けられていなかったり、補助金額が異なったり、といったことがあります。
空き家といっても、その状況を見るといくつものタイプがあります。特定空き家や管理不全空き家を含めた空き家の定義について、こちらのコラムで説明しています。
空家放置は所有者の負担増に!
自治体等が対策に取り組んでいるものの、空き家が減少する傾向はみられません。2023(令和5)年の住宅・土地統計調査では、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空家」は385万戸で、2018(平成30)年と比べ37万戸増加しています。
この増加の原因や空き家所有者への影響などについて説明します。
マトイの無料ご相談・お見積りでは、さまざまなご相談が寄せられています。そのなかには所有する空き家の処分に関するものなどもあります。空き家やご自宅などの解体および関連することでお悩みがありましたら、どうぞマトイをご利用ください。
マトイは東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で活動をしています。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
空き家問題の原因
適切に管理されていない空き家が増えると、そこを中心として害虫・害獣の発生や住み着き、ゴミの投げ入れ・放置、それらから発生する悪臭、家屋の老朽化の促進、不審者の侵入などが起こります。それによって敷地内はもちろん、周辺環境の悪化から住民の安全や衛生が侵されてしまいます。
では、なぜそういった空き家は増えてしまうのでしょうか。その原因として挙げられるのは次の3点です。
① 管理できない
相続したものの、所有者自身が居住している場所から離れているなどの理由から適切な管理ができない。
② 費用がかかる
管理には費用がかかる。だからといって、解体や建て替え・リフォームにも費用がかかり、その負担が大きい。
③ 更地にすると固定資産税が高くなる
住宅が建っている土地は、「住むための土地」として住宅用地の特例が適用。税制上それによって固定資産税が安くなる仕組みになっている。更地にするとこの特例が適用されず、固定資産税が高くなってしまう。
空き家増加の原因として挙がる上記3点のなかでも、③の特例がもっとも影響していると考えられています。
空き家放置は所有者の負担増に!
空き家、とくに管理が適切にされていない空き家の増加を受けて、国も積極的に対策を進めています。
空き家対策の根拠となる空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)を段階的に改正し、それによって、敷地内に建物があっても管理状態によっては住宅用地の特例が適用できなくなるようになりました。これによって固定資産税等がそれ以前よりも増加することで、所有者の経済的負担は増大することになります。
具体的には、特定空家や管理不全空家に指定されても適切な管理を行わないでいると、勧告が出されて特例措置が受けられなくなります。
それだけではありません。勧告にも応じないと命令が発令されます。この命令に違反すると過料(50万円以下)が徴収され、行政によって強制的に建物が解体撤去され、それらに要した費用を請求されます。
通常の空き家の維持管理はもちろん、解体撤去等も、所有者自身が判断して行う場合は、予算計画やそのスケジュールは所有者自身のペースで進められます。しかし、行政によって行われる場合は、あくまでも行政のペースで進められます。
税の軽減措置が適用されなくなる、固定資産税が増える、管理不全空家・特定空家の指定、それに続く行政からの指導・勧告・命令といったアプローチ、行政代執行等のプレッシャーなど、空き家を放置しておくことで、経済面だけでなく精神面での負担も加わって空き家所有者の負担はより増大します。
こちらのコラムでも、空き家のデメリットについて説明しています。どうぞこちらもご覧ください。
空き家処分のメリット
このように空き家を放置したままにしておくことで、所有者の負担はより大きくなってしまいます。しかし、行政の空き家対策には、所有者の負担を軽くするためのものもあります。
その1つが、「空き家発生を抑制するための特例措置」です。
これは一定の要件を満たしたうえで早期に空き家やその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を特別控除できるというものです(相続人数が3人以上の場合は2,000万円)。これには期限があって、現時点(当コラム掲載の2025年2月)では適用期間は2027(令和9)年12月31日まで延長されています。
できれば早く処分するのがおススメ
所有している空き家に対して利活用の予定がない、適切かつ定期的な管理ができない、管理のための負担が大きいなどと感じている場合は、できるだけ早く空き家を処分することをお勧めします。
処分方法には更地や古家付き土地として売却する、改修や建て替えなどして賃貸物件として活用するなどいくつかの方法があります。しかし、更地での売却や建て替えなどでは、空き家の解体工事が必要になり、その費用負担から行動に移せない方もいらっしゃいます。その場合には、空き家が所在する自治体に空き家解体のための補助金制度があるか否かを確認してみましょう。そして補助金制度が整っているようであれば、それを活用することで空き家処分に伴う費用負担が軽くなり、行動しやすくなることでしょう。
いずれにしても、利用目的が明確でない空き家を所有し続けることは、所有者の負担を増やすことにつながると思われます。今後の行政の空き家対策などの動向も含め、早めに処分することで負担が解消されます。
空き家の対処方法にはいくつかの方法があります。こちらのコラムでそれらについて詳しく説明していますので、どうぞお読みください。
空き家を解体する際に活用可能なさまざまな補助金
空き家の解体処分に対する補助金として、次のような内容のものがあります。
○老朽危険家屋解体補助金
老朽化が進み、倒壊の危険性がある空き家の解体費用を補助。
○危険廃屋解体撤去補助金
老朽化以外の理由で、危険があると判断された家屋の解体撤去を補助。
○空き家解体補助金
地域の安全や景観に悪影響を与える放置された空き家の解体撤去を補助。
○木造住宅解体工事費補助事業
耐震診断を経て倒壊の可能性が高いと判定された建物の、解体費用の一部を補助。
こちらのコラムでも老朽空き家の解体費用や補助金等について説明しています。どうぞお読みください。
東京都における空き家解体で活用できる補助金
空き家を含めた家屋の解体に対する補助金は、自治体によって補助金の種類や内容などが異なります。ここでは、東京都内における空き家解体で活用できる補助金制度の一部をご紹介します。
【東京都文京区の空家等対策事業】
○事業の概要
管理不全によって危険が常態になっている空き家等について、所有者等からの申請に基づき、文京区が空き家等の危険度を審査。さらに除却後の跡地が行政目的に利用可能かを検討。
事業対象と認定されたら、文京区と跡地利用契約を締結後に、所有者が除却を行う。その後、跡地を区が10年間無償で借り受け、行政目的で利用。
そのほか、文京区内に所在する空き家所有者や権利者の空き家に関する悩みに対して、専門家による無料相談事業も実施。
○助成金額
200万円(消費税を含む)を上限とした、除却に要した費用を交付。
【東京都墨田区の老朽危険家屋除却費助成制度】
○事業の概要
老朽建物等が「不良住宅」に該当するか否かを墨田区職員または墨田区の委託を受けた者が現地調査によって判定し、不良住宅と判定されたら所有者に対して除却費を助成。
○助成金額
除却費用の2分の1で、上限を50万円まで助成。ただし、無接道敷地(道路に接している敷地が2m未満)の不良住宅の場合は、上限100万円。
【東京都渋谷区の空家等適正管理支援事業】
○事業の概要
空き家などが周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、適正管理を図る次の工事を行う場合、その費用の一部を助成。
・建築物の修繕、除却などを行う工事。
・建築物に付随する工作物および建築設備の修繕、除却などを行う工事。
・敷地に対する仮囲い、および管理看板などの設置を行う工事。
・敷地内における立木その他土地に定着する物などの選定および撤去。
・敷地内における害獣および害虫などの対策及び駆除。
・敷地内における廃棄物および不法投棄などの撤去および処分。
○助成金額
消費税を除く費用の50%(千円未満は切り捨て)。ただし、不良住宅の除却などを助成する場合は50万円を限度とし、それ以外の工事などを助成する場合は10万円を限度とする。
【東京都杉並区の老朽危険空家除却費用の助成制度】
○事業の概要
周辺の生活環境に著しい影響を及ぼす、特定空家およびそれに準じる倒壊の危険性が高い老朽危険空家に対して、除却工事費の一部を助成。
○助成金額
除却工事費の80%、または150万円のいずれか低い額を助成限度額とする。
【東京都板橋区の老朽建築物等除却費助成事業】
○事業の概要
板橋区内の特定空家または特定老朽建築物に認定された建築物の除却を行う場合、費用負担の軽減を図るためにその費用の一部を助成。
○助成金額
建物の除却は、除却する延べ床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じた額。
工作物等の除却では、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じた額。
いずれも100万円を上限。
家屋の解体に関する助成金等は空き家以外にもあります。その1つに不燃化特区制度として木造住宅密集地域における老朽家屋の解体や建て替えの助成があります。こちらのコラムでそれを取り上げていますので、参考になさってください。
まとめ
皆様が所有している空き家は多くの場合、ご実家やご親族の方々から引き継いだものでないでしょうか。それはご自身の思い出ともつながることから、利用予定はないものの処分できないままでいる……というものもあると思います。
しかし、実際には空き家の存在が所有する方々の負担になっている場合もあります。そこから、利用目的のない空き家は早い段階で処分することをお勧めします。
それに際して、今回のテーマとした補助金は経済的な負担を軽くするものとして、ぜひ利用をお勧めします。
しかし、処分に際しては、どのような形で処分するべきか、更地にする場合は建物の解体はどのように依頼すべきか、費用はどの程度を考えておくべきか、等々、考えるべきことがたくさんあります。
まずはいま所有している空き家をどのようにするべきかを考えてみましょう。解体して売却する、古家付きのままで売却する、建て替え等をして利活用を進めるなど、方向性を決めます。そのあとは、ぜひマトイにお声掛けください。
マトイでは解体工事はもちろん、それに付随するいろいろな相談事にも対応しています。空き家対処の方向性を決めたら、それから先どのように進めていくべきか、なども含めて有意義なご提案をさせていただきます。
東京都をはじめ、埼玉県、神奈川県、千葉県を活動範囲としています。無料お見積りなどのご提案の際には、これら地域の補助金の活用などについても、皆様にとって有意義なご提案ができるように日々、情報収集を行っています。
どうぞお気軽にマトイの無料お見積り・無料ご相談をお気軽にご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
手壊し解体が必用なケース。費用や手順は?
Next
30坪の家。解体費用を安く、スピーディーに工事を進めるコツ!








