更地返還は義務ではない? 返還までの4つの流れと解体費用
かいたいコラム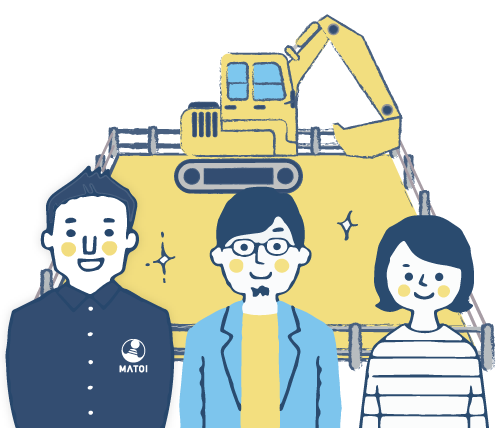
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
土地を借りて、そこに家屋を建てている方も多くいらっしゃいます。
その場合、借地の契約が満了となったり、なんらかの理由で契約解除されたりしたときには、原則として建物を解体撤去して土地を返却するとされています。しかし、解体費用は100万円を超えることも多く、借主にとって大きな負担です。
実際、借地を返却する際には必ず更地にしなければならないのでしょうか?
今回は借地を返還する際、必ず更地にする必要があるのか、そして借地にある建物の解体の流れや費用などについて説明します。
借地にある建物の解体では、解体前の準備がやや複雑になりがちです。「こんなとき、どうしたら……?」とお困りのことがありましたら、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事を行っているマトイの無料ご相談・無料お見積りをご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
更地にして返還する場合のポイントと4つの流れ
借地を返還する場合、原則は借地上の建物は借地人が解体撤去して更地にします。しかし、建物の解体撤去を必要としない場合があります。
まず更地にして返還する場合について説明しましょう。
更地にして返還する場合
更地にして返還するケースには、次のようなものが挙げられます。
・借地契約に「更地返還」が明記されている。
・借地契約が新法の定期借地権である場合、契約期間満了時に更地返還が義務。
・契約書に更地返還の記載はないものの地主が希望する場合、解体費用等の交渉を行って更地返還する。
・借地権付き建物としての売却が難しい場合。
・次の契約更新が拒否された場合。
更地にして借地返還手続きの4つの流れ
借地にある建物を解体撤去して更地にする場合の流れについて説明します。
Step1 契約書の記載事項を確認
最初に確認すべき大切なことは、借地契約がいつまでなのか、そして借地権がどのような種類なのか、という点です。
これらは契約書で確認します。契約書には、「借地権の種類」「存続期間」のほか、「賃料と支払方法」「借地上の建物の処分方法」などが記載されています。
とくに大切な借地権の存続期間は、途中で解約することができません。そして、この期間は旧法と新法のどちらで契約しているか、新法での契約ならば普通借地権と定期借地権のどちらで契約しているかによって変わります。
まずは契約書を開いて、借地権の存続期間と処分方法について、どのような契約内容になっているかを確認してください。
Step2 貸主への報告・交渉
契約内容を確認したら、貸主である地主に借地権を返還する旨を伝え、それにあたって必要なことの交渉に移ります。この段階で貸主と話し合うことは次のような点です。
・借地を返還することの報告。
・いつまでに更地にして返還するか。
・解体費用の負担についての確認。原則として、更地返還の場合の解体費用は借主が負担します。ただし、契約に特例がある場合や、返還理由が貸主である地主側の都合である場合には、費用負担について交渉してみましょう。
なお、このステップを踏まずに解体工事等を行うとトラブルを引き起こしかねません。必ず行う必要があります。また、最初だけではなく、最終的に返還に至るまでの間の進捗に併せて、適宜、報告や相談を行いながら進めていくようにしてください。
Step3 解体業者の選定と解体工事
地主への報告や交渉が済んだら、解体工事に向けて解体業者の選定と解体工事のための準備を行います。
解体工事費用は定価があるわけではなく、地域や業者によって違いがあります。また、地主や知人に業者を紹介されたり、指定されたりすることがあるかもしれません。
いずれにしても施主となって費用を支払う立場となった人は、慎重に業者を選びましょう。
その際、費用の相場を知って誠実に仕事に当たる業者を選びたいものです。そのためには、できるだけ複数の業者から見積りをとって比較・検討して業者を選定することをお勧めします。
そのようにして解体業者を決めたら、その業者の担当者と相談しながら近所への挨拶回りや家屋内の不用品の処分などを進め、解体工事を開始します。
施主となる場合、ある程度解体工事の流れを知っておくことで、業者との打ち合わせなどもやりやすくなります。
こちらのコラムで解体工事の流れについて細かく説明していますので、ご覧ください。
Step4 更地の返還と建物滅失登記
解体工事が完了したら、更地の状態になった土地を貸主に返還します。それとともに借主は完工の1か月以内に「建物滅失登記」を行う必要があります。
建物滅失登記は、その建物がなくなったことを登記するもので、法務局に届け出ます。これを行わないと、登記上、建物が存在したままになるので固定資産税等の税金が課税されたり、貸主がその土地を何らかに利用しようとする際にトラブルを引き起こしたりすることがあります。
「登記」と聞くと何やら難しそうですが、こちらのコラムで建物滅失登記について説明していますので、ご覧ください。
返還に備えて知っておきたい借地権の種類
借地権の根拠となる法律は、現在、通称・旧法と呼ばれている「借地法」と、通称・新法と呼ばれている「借地借家法」があります。これは借地借家法が成立した1992(平成4)年が区切りとなっています。
旧法と新法に基づく借地権のポイントを以下に挙げます。
【旧法に基づく借地権に関して】
○旧法に基づく借地権は、旧(法)借地権という。
○木造等の非堅固建物の場合は20年間、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの堅固建物は30年を期間として地主と賃貸借契約を結ぶ(双方の合意があれはそれ以上も可)。
○建物所有を目的とした契約で、地主は建物がある限り一方的に契約破棄できない。
○契約が終了する際、借地人は建物の買取を地主に請求できる権利をもつ。
【新法に基づく借地権に関して】
○新法に基づく借地権は、「普通借地権」と「定期借地権」がある。
○普通借地権は契約期間が30年間で、最初の更新では20年間、それ以降の更新では10年間の契約となる。
○普通借地権では、建物買取請求権を行使したり、地主との交渉によって建物を解体しないで返還したりすることが可能。
○定期借地権には一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3つがある。
○一般定期借地権の契約期間は50年以上。更新はできず、契約満了時には更地返還する。
○建物譲渡特約付借地権は、30年以上の契約期間。更新はできないが、返還時に建物解体の必要はない。契約期間終了後、賃貸として家賃を支払いながら住み続けることが可能。
○事業用定期借地権は用途を事業用に限定。契約期間は10年以上50年未満。契約期間完了時には更地にして返還。
こちらのコラムでは、借地権付きの建物の処分について説明しています。借地権付き建物の処分をご検討中の方は参考になさってください。
義務ではない。更地返還をしなくていい場合
借地を返還する際、必ずしも更地にする必要がないケースもあります。
そのケースについて説明していきます。
建物買取請求権をもつ旧借地法や普通借地権で契約している場合
「建物買取請求権」とは、借地人が地主に借地の上にある建物を買い取るように請求できる権利です。
これは借地借家法によって定められているもので、旧借地権や新法の普通借地権での契約において、契約期間満了などの一定の要件に当てはまった場合に行使が認められます。なお、そのためには次の3要件すべてを満たしている必要があります。
・借地契約の期間が満了。
・借地契約の更新がない。
・借地に建物がある。
ただし、借地人に地代の未払や遅滞、重大な契約違反などがある場合は、地主は建物買取を拒否できます。
まずは借地権の契約書をみて、旧法による契約か、新法であれば新法のどの契約であるかを確認しましょう。
契約内容に特約がある場合
借地契約書に「建物を解体しないまま返還する」といった内容の特約が記載されている場合は、建物の解体撤去の必要はありません。
地主との合意がある場合
地主が、借地権返還にそこにある建物をそのまま利用したい場合や、買取りを希望する旨の申し出があって、その内容に借地人と地主が合意した場合。
第三者へ借地権売却をする場合
借地権は、第三者に売却することも可能です。そのため、譲渡先となる相手が建物を含めての購入を希望もしくは承諾すれば、建物を解体する必要はありません。
ただし、この場合も多くの場合、地主の承諾が必要になります。
定期借地権以外の場合
一般定期借地権では契約終了時に更地返還が義務付けられていますが、普通借地権や旧法借地権の場合は交渉次第で解体を免除される可能性があります。
借地を更地にする際の解体費用
借地権の種類をはじめとした契約内容を確認して、借地の返還に向けての準備を進めていきます。
その際に大切なこととして、予算計画があります。更地を返還するためにかかる費用、そしてその後の計画に必要な費用などを併せてどのくらいの費用が必要になってくるのか、その費用をどのようにして捻出するかなどです。
建物の解体費用はまとまった金額が必要になり、解体費用の有無によって予算計画は大きく変わります。
解体費用の相場
解体費用には定価がありません。そのため、地域や業者によって異なります。
とはいえ、計画を立てるためにも「だいたいどのくらいの費用がかかるだろう……?」とある程度の金額の把握をしたいと思うかもしれません。
建物の解体費は、解体する建物の構造や延べ床面積などからだいたいの相場を計算することは可能です。その計算式は次の通りです。
○解体費用の相場=解体する建物の延べ床面積(坪)×坪単価
○構造別の坪単価
木 造:30,000円~
鉄骨造:40,000円~
鉄筋コンクリート造:50,000円~
○解体費の相場の計算例:延べ床面積50坪の木造家屋
50(坪)×30,000(円~)=150万円~
解体費については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞこちらもお読みください。
更地解体する場合の解体費用に関する注意点
更地解体する際の流れはすでに説明していますが、事前に注意すべき点についてあらためてここで説明します。ここに挙げる点は、とくに解体費用にも大きな影響を与える可能性があるので注意しましょう。
契約内容を確認
借地の賃貸借契約書を必ず確認しましょう。そこには借地権の種類とともに「更地返還」の義務や「建物買取」などについて記載されている場合があります。契約内容によって建物を解体しないで返還できる場合もあります。
まずは契約内容を確認して、経済的負担を少なく効率的に借地返還が行えるようにしましょう。
解体費用の相場を把握
解体費用には、それを決める一定の基準のようなものはなく、業者によって、また地域の物価などによって異なります。
また、解体する建物の構造によっても解体費用は大きく異なります。木造よりも鉄骨造が、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造の建物のかいたい費用が高くなります。これは建物が謙子になるほど解体に手間がかかるためです。
複数の業者から見積りを
できるだけ避けたいのは、最初から1つの業者に決めてしまって、他との比較検討をしないことです。それでは、提出された見積り内容が安いのか、高いのかの比較検討をしにくい状況です。
できれば複数の業者から見積りをとりましょう。そして比較検討することで、費用の妥当性はもちろん、業者の対応や仕事の質の良し悪しを推し量ることができます。
とくに注意したいのは、極端に見積金額が安すぎる業者です。見積り金額が安すぎる場合、産業廃棄物の廃棄処分などをきちんと行わずに不法投棄していたり、手抜き工事をしていたりする可能性があります。また見積り段階で必要な工事を入れず、工事に入ってから追加工事として後から高い費用を請求するような悪徳ケースもあります。
マトイでは当社サイト上で無料お見積り・無料ご相談に対応しています。どうぞ、お気軽にご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
追加工事・追加費用発生の可能性を考慮
解体工事を進めていくなかで、予定外の工事が必要になる場合があります。
例えば、地中に古い瓦礫が出てきた、解体を進めるうちに過去に修繕していた箇所にアスベスト含有建材が使用されていた、などといった見積り時には想定されていなかったようなことです。
こういったことは必ずしも起こるわけではありませんが、起こらないとは限りません。この例でいえば、地中の瓦礫を撤去やアスベスト処理を行う必要があります。そしてこれらは追加工事となり、費用が発生します。そのため、事前に業者と相談し、予算を確保しておく必要があります。
こちらのコラムでは追加工事についてより詳しく説明しています。どうぞごちらのコラムもお読みください。
地主との交渉
スムーズに借地を返還するためには、地主との交渉が欠かせません。まず契約期間満了を迎える際に返還する旨を伝え、それにあたっての打ち合わせを進めていきます。
一番の課題は更地返還するか否かで、借主にとって一番いいのは、地主に建物の買取をしてもらうことでないでしょうか。そのために契約内容の確認はもちろん、契約内容に建物買取や更地返還の記載がなかったとしても、建物買取に向けた交渉を進めてみることをお勧めします。
補助金申請に向けた準備
更地返還する場合、その費用は原則として借主が負担しますが、補助金等を活用してその負担を軽くできます。
自治体のなかには、家屋の解体費用の一部を負担する補助金や助成金制度を準備しているところがあります。まずはその制度の有無を知らべ、ある場合には申請要件や申請方法など、活用に向けた準備を進めておきましょう。
解体費用を抑えるためのポイント
家屋を解体する場合、その費用は多くの場合、100万円以上になります。その負担は大きなもので、できれば少しでも減らしたいと思うはずです。そこで、そのためのポイントを説明します。
自分で処分できるものは自分で
解体工事に取り掛かる前に、借主は建てた建物のなかにある家具や不用品を処分します。この処分がじゅうぶんでないまま解体工事に移行すると、残されたものは廃棄物として他の廃棄物とともに処分されることになります。
解体にかかる費用のなかでもっとも多くを占めるのが建物本体を解体するための費用です。次にかかるのが解体工事によって排出される廃棄物の処分費用ですが、この場合、産業廃棄物扱いになって処分費用は高額になります。ここに残置物が加わることで廃棄物量が増え、処分費用はさらに高くなってしまいます。
廃棄物処分費用が高くなるのを抑えるため、建物内にある不用品は可能な限り自分たちで処分することが、費用を抑える大きなポイントになります。
自治体の補助金・助成金を活用
自治体のなかには、家屋解体に当たって解体費用を一部補助する制度を設けているところがあります。これを利用することで、解体費用の経済負担をかなり抑えられます。
前項の「解体費用の注意事項」でも説明しているように、遅くとも更地返還の検討を始めた段階から、補助金等の制度の有無や補助内容、申請要件などの情報収集を開始し、積極的に利用するようにしましょう。経済的負担がかなり軽減されます。
家屋の解体に対する補助金や助成金などは、空き家や老朽化が進んでいることなどの条件があるものや、家屋全般を対象にしているものなどもあります。
マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事を行っていますが、こちらのコラムで東京都の補助金・助成金等について詳しく解説しています。どうぞ、参考になさってください。
まとめ
借地返還ではどのような内容で契約しているかに加え、借地権の種類によって返還の内容が異なってきます。
ですから、建物を解体して返還するか否かという点とともに、どのような種類の借地権であるのかもしっかりと確認したうえで、準備を進める必要があります。
ここまで説明してきたように借地権の返還に当たっては、契約内容の確認、建物解体の検討、解体に向けて業者選定等から始める準備、解体工事といったことが必要になります。解体工事に至るまでの契約内容の確認、建物解体の検討と解体業者の選定などはほぼ同時進行に近いペースで進めることになるでしょう。
そんなとき、マトイをはじめとした解体業者を相談相手としてご利用ください。解体工事依頼以前であっても、良心的で誠実に解体工事業に取り組む業者であれば、皆様のお問い合わせに誠実に向き合います。どうぞお気軽にお問い合わせください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
もう迷わない! ナットクできる解体屋を選ぶ一番の方法とは?
Next
空き家問題とは、チャンスに変わる? 解体と活用のリアル








