道路使用許可を取得して安全に解体工事を行う方法
かいたいコラム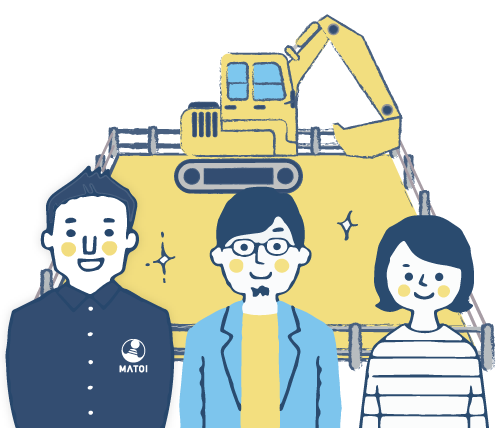
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
解体工事を行う際には、事前にいくつかの届け出が必要です。その1つが「道路使用許可」というものです。
重機やトラックなどの工事車両が現場付近の道路を通って現場に入る際に、欠かせない届け出です。今回はこれについて取り上げます。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事およびリフォーム工事等をお請けしている会社です。これらの工事ではさまざまな届け出・手続きが必要になりますが、それらを含めて的確かつ迅速に対応しています。どうぞ、安心してお任せください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
道路の使用規制と工事の安全管理
普段、何気なく使っている道路ですが、これには警察や行政によって一定のルールが定められています。誰もが、いつでも自由に使えるわけでないのです。
道路の使用を規制する最大の理由は、人々の安全を守るためです。
例えば、工事や災害が起こった際には、行政や警察などによって通行止め・通行禁止になったり、駐停車禁止になったりします。これは人々の安全を守り、交通を円滑にするためです。
解体工事では重機などの特殊車両や大型トラックなどが現場に出入りします。これによって周囲の通行者や一般車両に何らかの影響を与える場合もあります。そのため、事前に道路使用に関する届け出をすることになります。
解体工事で気を遣う安全管理の1つに重機の取り扱いがあります。こちらのコラムでは重機による騒音や振動対策、安全対策などを説明しています。どうぞご覧ください。
道路使用に関する法律
道路の使用規制や届け出の根拠となるものには、「道路交通法」、「道路法」、「地方自治体の条例」があります。
ここで、「道路交通法」および「道路法」について簡単に説明しておきます。
道路法
道路法は、道路の整備・管理・保全などに関する基本的なルールを定めている法律です。公共の福祉と交通の発達を目的に、道路網の整備や道路の安全と機能の確保、そして公共の福祉の増進を役割としています。
道路交通法
道路交通法は、交通の安全と円滑さを守り、道路に起因する事故や障害を防止するために、歩行者・車両・自転車等の通行ルールを定めています。
道路使用許可とは
道路使用許可は、公共の道路を一時的に占有・使用するための許可です。
建物を解体する際には、事前に必ずこの手続きを行わなければなりません。
解体工事の際に現場と公道を隔てて安全を確保する物に仮囲いがあります。こちらのコラムでは仮囲いについて取り上げていますので、今回の許可と併せて参考にしてください。
道路使用許可の根拠となる法令
道路使用許可の根拠は、「道路交通法第77条」になります。
(道路の使用の許可)
第77条
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
この法令に基づく道路使用許可には次の4つがあります。
【1号許可】
道路で工事や作業を行う場合。
解体工事、足場設置、電柱工事、配管工事、搬出入作業などの際に届け出る。
【2号許可】
道路に工作物を設ける場合。
看板、アーチ、広告板、公衆電話ボックス、街路灯の設置などの際に届け出る。
【3号許可】
移動しないで店舗等を出す場合。
露店、屋台、キッチンカー、フリーマーケットの出店などの際に届け出る。
【4号許可】
一般交通に著しい影響を与える行為を行う場合。
祭礼、パレード、ロケ撮影、マラソン大会、デモ行進などを行う際に届け出る。
管轄
道路交通法に基づく道路使用許可の届け出は、警察署(公安委員会)の管轄となります。
目的と必要になる理由
道路を本来の交通とは異なる工事やイベントなどで使用する場合、交通の妨げや危険が生じないようにする必要があります。そのため、具体的な目的として次のようなことを挙げています。
〇交通の妨害や危険を防止
許可を得るのを通じて、通行人や車両の安全を守るための誘導員配置、標識の設置などの対策を事前に確認・指導します。
〇社会的・公益的活動を円滑に実施
社会的に価値のある活動を認めることをとおして、地域の発展や文化活動などを支援。
〇道路本来の役割を維持
道路の公共性や利便性といった本来の役割を妨げるような無秩序な使用を防ぎます。
申請の必要書類と流れ
【道路使用許可申請に必要な書類】
・道路使用許可申請書
申請者の氏名・住所、使用目的、場所、期間、方法、現場責任者に関する情報等を記入します。
・添付書類
使用場所周辺の地図。
工作設置の場合は、その仕様書・設計図。
必要に応じて交通誘導計画書。
その他、警察署が必要と認める資料。
【申請の流れ】
ステップ1/事前相談
許可が必要か否かを警察署にも事前相談する。
ステップ2/必要書類等の準備
必要に応じて現地測量などを行いながら、見取り図や仕様書など必要書類を整える。
ステップ3/申請書の提出
申請書および添付資料を2部ずつ、警察署の窓口に提出。
ステップ4/審査・許可証受領
審査を受けて許可が下りたら、許可証を受け取る。
解体工事では道路使用に関する届け出のほかにもさまざまな届け出が必要になります。こちらのコラムで、それらについて説明していますので、併せてお読みください。
状況で必要になる道路使用に関する届け出
解体工事を行う際には、道路使用許可は必ず取得しなければならないものです。加えて、「道路占用許可」や「交通規制申請」など現場環境や作業内容などによって必要な届け出があります。
道路占用許可
道路占用許可は、電柱・ガス管・工事用足場などの工作物、物件、施設等の設置によって、継続的に道路を使用する場合に必要になる許可です。
なお、この許可の対象となる道路は次の4種類です。
・高速自動車国道
・一般国道
・都道府県道
・市町村道
道路占用許可の根拠となる法令
道路占用許可は道路法32条に基づくものです。
道路法第32条 道路の占用の許可
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用するとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
管轄
国土交通省の管轄となります。また、占用する道路の種類によって担当窓口が異なります。
・高速自動車国道……国土交通省の道路管理担当課
・一般国道……国土交通省の道路管理担当課
・都道府県道……都道府県の道路管理担当課
・市町村道……市町村の道路管理担当課
目的と必要になる理由
電柱や看板設置などによって道路を継続的かつ独占的に使用する場合、道路本来の機能である安全かつ円滑な交通を守るために行います。
申請の必要書類と流れ
【道路占用許可の必要書類】
・道路占用許可申請書
・占用する場所の位置図や見取り図、その周辺の地図
・占用する工作物の構造図や設計図
・工事の工程表
・占用物件設置工事完了届など
【道路占用許可申請の流れ】
ステップ1/事前相談
占用する道路の種別を確認し、道路管理者である国・県・市町村に占用の内容を相談し、許可が必要か否かを警察署へ事前相談する。
ステップ2/図面・資料作成
占用する物件の位置図、構造図、仕様書、工程表などを準備。
ステップ3/申請書の提出
申請書および添付資料を書面または自治体によってはオンラインで申請。
ステップ4/審査・協議・許可取得
管理者による審査を受け、必要に応じて補正・追加資料を提出。許可証を受け取る。
ステップ5/工事着手
許可証を受領後、工事開始。完了後は「工事完了届」を提出。
その設置場所や範囲などが道路交通法にも関係する足場や養生について、こちらのコラムも参考にしてください。
交通規制申請
工事やイベントなどで一時的に交通の流れを止めたり、変更したりするときに申請します。
交通規制申請の根拠となる法令
道路交通法第4条による公安委員会の権限、同法第5条による警察署長の権限、同法第8条による通行の禁止・制限などに基づいて、公安委員会や警察署長が通行止め・車線規制・一方通行・駐停車禁止などの交通規制を実施。
管轄
警察署(公安委員会)
目的と必要になる理由
〇道路における危険防止
工事やイベントによる交通事故等のリスクを減らします。
〇交通の安全と円滑さの確保
歩行者や車両が安心して通行できるようにします。
〇交通公害の防止
騒音・振動・排気ガスなどによる住民の生活環境への悪影響を防止します。
申請の必要書類と流れ
【交通規制申請の必要書類】
・交通規制申請書
・規制図や見取り図
・交通誘導計画書
・疎明資料
・車両関係書類
・必要に応じて道路使用許可や道路占用許可
【申請の流れ】
ステップ1/事前相談
規制予定地の管轄警察署に、規制内容・期間・必要書類を確認。
ステップ2/必要書類等の準備
規制図や交通誘導計画、疎明資料などを作成。
ステップ3/申請書の提出
所轄警察署の交通課に申請書と添付資料を2部提出。
ステップ4/審査・協議・許可取得
警察署による審査を受け、必要に応じて補正・追加資料を提出した後、許可取得。
ステップ5/規制実施
許可証受領後、規制を実施。完了後は報告書提出が求められる場合がある。
解体工事では業者の選定や不用品の処分から解体後の建物滅失登記に至るまで、施主様にとって行うことが盛りだくさん。マトイでは施主様のパートナーとして、細かく進行についてのご案内・ご相談、そしてサポートを担当者が最後までしっかり行います。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事は、どうぞマトイにお任せください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
道路に関する複数の届け出が必要になるケース
解体工事をはじめとする建設工事では、道路使用許可のほかにここまでに説明した道路占用許可や交通規制申請など複数の届け出が必要になるケースがあります。その具体例として、次に挙げるものがあります。
【道路使用許可と道路占用許可が必要な例】
・住宅密集地での木造家屋の解体。
重機搬入に際して道路使用許可、歩道にはみ出した足場のため。
・現場前面の道路が狭く、資材置き場が道路上になる。
一時的な道路使用に加え、仮囲いが継続的に道路を占用するため。
・現場が角地で、2方向の歩道に足場がかかる。
交通誘導と足場専用の両方が必要。
・アスベスト除去を伴う解体工事で、養生シートが道路面に張り出す。
養生作業の一次使用とシートの継続的占用。
【道路使用許可・道路占用許可・交通規制申請の3つが必要な例】
・道路に面した壁を重機で解体撤去するときのように工事中に通行止めや片側通行が必要な場合、道路使用許可・道路占用許可・交通規制申請の3つが必要になります。
事前協議をしておくといいケース
各許可取得前に管轄の担当窓口に相談することは前述しました。これを「事前協議」ともいいます。ここでは、事前協議について説明します。
事前協議とは
事前に相談すること=事前協議は、この道路交通に関する許可取得に際しては「道路使用に関する事前協議」といいます。
道路使用許可をはじめとする各種許可を申請する前に、警察や自治体の担当窓口に工事の内容や安全対策について事前に相談・調整します。
とくに解体工事や建築工事においては、とても重要なプロセスです。現場周辺の安全対策の内容によっては周辺の交通や歩行者の安全に大きく影響を与えるおそれがあります。さらに近隣トラブルの予防にもつながり、工事計画の全体にも影響を及ぼすものなので、とても重要なプロセスです。
事前協議する内容
事前協議で検討する内容として次のようなことが挙げられます。
・道路の使用目的・範囲・時間帯、
・誘導員の配置計画、
・看板・バリケードの設置方法、
・近隣施設(学校・病院など)への配慮、など。
事前協議をしておくといいケース
とくに事前協議を行っておくといいケースとして、次のようなものが挙がります。
・現場に面した道路が狭い、もしくは通学路や生活道路に面している。
・足場や仮囲いが歩道にはみ出す。
・作業の都合上、通行止めや片側通行が必要になる。
・周辺の交通量が多い、もしくは近隣に学校や病院がある。
・道路使用許可のほかに道路占用許可や交通規制申請など複数の許可が必要。
解体工事に当たっては、事前協議を含めて解体工事の全体の流れを把握しておくことが大切です。こちらのコラムで流れや必要な手続きなどを説明していますので、参考にしてください。
各種届出を行わなかった場合の罰則
法令に基づいたこれらの許可を得ないまま道路を使用したり、交通を勝手に規制したりすることは、法令違反になります。そのため、違反に対して罰則が科せられる可能性があります。
道路使用許可を得ないまま道路を使用した場合
この場合の罰則は、3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金となります。
道路使用許可に関する違反例
・未許可のまま足場や仮囲いを歩道にはみ出して設置、
・重機や資材を道路上に仮置きしたまま作業を開始、
・許可は得たものの警察署長が定めた時間帯や範囲などを守っていない、など。
違反回避に向けて
・着工前に所轄の警察署と事前協議を行う、
・許可取得後は、時間帯・範囲・誘導員配置などの条件を厳守する、
道路占用許可を得ないまま道路を使用した場合
道路占用許可を無届で行った場合、次のような罰則が科せられます。
1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金。
道路占用許可に関する違反例
・足場や仮囲いが歩道にはみ出しているが、占用許可を取っていない、
・無許可のまま看板や広告物を道路上に設置している、
・許可はとっているが占用面積や期間が申請と異なっている、
・占用料(これは自治体や使用期間によって異なります)を支払わないまま継続使用している、など。
違反回避に向けて
・事前協議の実施、
・占用範囲、期間、構造物の図面を正確に提出、
・占用料の算定と納付を忘れずに行う、など。
交通規制申請を行わないまま交通規制をした場合
交通規制申請を行わないまま交通規制をした場合、次の罰則が科せられます。
3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金。
交通規制申請に関する違反例
・未申請のまま通行止めを実施、
・未申請のまま、工事車両の出入りのために片側交通を実施、
・誘導員を配置しないで、交通の流れを勝手に変更、
・許可を取得したが、許可された時間帯や範囲を逸脱した規制を実施、など。
違反回避に向けて
・着工の前に警察署で事前協議を行う、
・必要書類を整えて申請をする、
・時間帯、範囲、誘導体制など、許可証にある条件を厳守する、
・近隣への説明を事前に行って苦情対応の体制を整える、など。
まとめ
解体工事では、今回取り上げた道路に関する許可のほか、各種届出が不可欠です。もしも無許可のまま工事を始めてしまうと、法令違反となり何らかの形で罰せられる可能性が出てきます。それだけでなく、事故や近隣トラブルの原因にもなります。
施主様としてもそれに対して心配していることと思います。
マトイでは事前協議から申請手続き、そして現場の安全管理対策まで一貫した対応で、安心・確実な解体工事を実施します。もちろんそれは道路交通以外の手続きについても同様です。また、施主様が行う手続き等についても、施主様のご都合・ご要望によって代行して行うことも可能です。
いずれの場合も、法令遵守と現場がある地域への配慮も徹底して工事に当たります。地域配慮を徹底し、信頼される工事をお約束します。
マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事およびリフォームなどをお請けしています。法令を遵守した対応と安全かつ確実な解体作業および対応で定評のあるマトイです。どうぞお気軽にお声をおかけください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
ツーバイフォー解体の費用・日数・注意点|知っておきたい構造の特徴
Next
建設リサイクル法に基づく分別解体の義務と再資源化の手順







