古民家を自分で解体できる?
かいたいコラム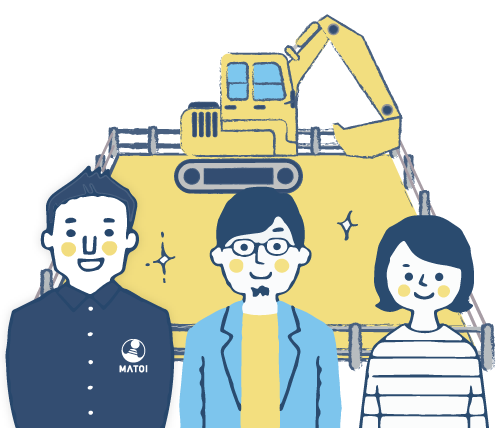
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
多くの方が何らかの趣味をお持ちと思います。そのなかにはハンドメイドやDIYなどで、身の回りの物を手作りして楽しんでいらっしゃる方も多くいらっしゃることでしょう。
そういった方々のなかで、空き家や古民家の解体が必要な状況を前に「自分で解体してみようか?」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。そこで、今回は古くなった家屋-古民家を自分で解体することについて取り上げてみます。
ご自身で家の解体をご検討の方も、費用等の参考としてマトイの無料お見積りやお問い合わせをお気軽にご利用ください。新たなプランが広がるかもしれません。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
古民家を自分で解体。その前に知っておきたいこと
自分で古民家を解体しようとする場合、その前に知っておくべきことがあります。次に説明することを知ったうえで、解体工事を自分で行うか否かを考えることをお勧めします。
業者に依頼するのと自分で解体するのとの違い
建造物を解体する場合、その大きさや規模などさまざまな要因が作業方法や作業量・作業効率に関係してきます。家屋の解体をする場合も同様です。
業者に依頼する場合は、現場に適した解体計画を立てて作業に臨みます。施主様は解体に際して、「あそこの柱は残してほしい」、「解体後は駐車場にするので、それに適した整地をして」というように、解体に伴う希望を業者に伝え、進捗を見守りながら工事終了を待つようになります。
しかし、自分で解体するとなると事情は全く異なります。
どのように解体作業を進めていくかの計画、重機をはじめとした解体に必要な機材の準備、必要な諸手続き、必要に応じて解体作業を手伝ってくれる人への依頼と説明、安全に作業を行うための装備、万が一のケガ等に備えての準備、これらを整えたうえでの作業の開始、そして廃棄物処理などなど、具体的に挙げたらきりがありません。
しかもこれらのすべてを自分で行えるわけではありません。例えば後に説明するアスベストの事前調査やアスベスト含有建材の対処などは業者に依頼しなくてはなりません。
まずは、作業に影響を与える要因について知っておく必要があります。
DIYで家屋の解体を行う場合に必要な情報を、こちらのコラムでもまとめて説明しています。ぜひ、お読みください。
造り
一口に古民家といっても、いつ頃建てられたかによって趣も構造も異なります。一般的に古民家と呼ばれる建物と現代の建物の違いとして次のような点が挙げられます。
DIYを趣味として、家のリフォーム等に慣れている方でも、この違いによって作業にも違いが生じるため、あらかじめ把握しておきましょう。
【屋 根】
現在は金属あるいはセメントを主成分としたスレートがメインです。しかし、古民家の多くは茅葺屋根や瓦屋根を使用しています。
現在では一般家屋で茅葺屋根を見ることはほとんどなくなりました。瓦屋根は現在も使用されています。瓦を固定したり、瓦と瓦の間を埋めたりするのに漆喰を使用していますが、これは10年ほどで経年劣化するために、メンテナンスが必要です。
ところがメンテナンスが行われず、古家になった家屋では、劣化が進んでいる可能性があり、屋根の解体にも倒壊などに対する十分な注意が必要になります。
【 壁 】
現代の住宅では、内壁材として主に石膏ボードが使われています。
一方、古民家では土壁を内壁としています。内壁に使用するのは漆喰や珪藻土で、これらは通気性、耐火性、蓄熱性が高く、断熱材としての役割も果たしています。ただし、解体においては石膏ボードよりも粉塵が多く発生するため、その対策も欠かせません。
【 床 】
床は居室では畳、廊下や台所などは板張りです。床張りの部分では、無垢材を使用しています。畳や無垢材は、調湿性、保温性、吸音性が高く、これらの風合いが日本家屋の風情を醸し出しています。
【 窓 】
窓の内側に障子を用いることで、部屋全体の明るさや日差しの調整をしています。また、障子の下半分をガラス窓にしたり、意匠を凝らした建具を用いたりしています。
今では製造が難しいような手の込んだものなどもあり、保存する場合は解体着工以前に取り外すなどの作業が必要です。
【 構 造 】
古民家は梁と桁といった木と木を組む伝統工法によって建てられています。一方、在来工法は柱同士を金属の部品を使用して固定しています。
在来工法と異なり、つなぎ合わせる金属部品がなく、木と木を組み合わせて組み立ててあり、しかも長年の荷重に耐えてきているので、柱等の状態にもよりますが、解体はかなりの力作業になります。
【 基 礎 】
古民家の基礎は、「玉石基礎」といって地面に置いた石の上に柱を立てます。また、少し新しい古民家になると、玉石ではなくてコンクリートブロックを使った「コンクリートブロック基礎」となります。いずれにしても、石やコンクリートブロックと柱を固定させていないことで、地震時の揺れを逃がす免震構造になっています。
玉石基礎やコンクリートブロック基礎には鉄筋は入っていません。そのため、解体時の作業負担は比較的軽いといえます。
古民家では今では使えないような貴重な木材が使用されているケースも多くあります。それらを再利用することも可能です。解体した家に使われていた木材等を再利用することについて、こちらのコラムで取り上げています。どうぞ参考になさってください。
状態
築年数が長ければ、経年劣化も大きくなります。それだけではなく、解体までに人が居住していたか、長期間空き家状態であったか、適切なメンテナンスや管理がなされていたか否かによって、その家屋の状態に違いが表れます。
経年劣化以外の要因によって起こる家屋の痛みを適切に判断することは、作業中の崩落等のリスク対策に直結します。
作業環境(スキル、機材、作業員人数)
解体作業を適切に行っていくためには、解体する建築物に応じた作業員人数、重機等の機材、そして作業員のスキルといった環境を整える必要があります。
解体する家屋の大きさ、工期、これらに見合った作業人数、基本的な工具に加えて重機やウィンチなどを揃え、作業に当たる人はスキルをもっていることが大切です。
アスベストの事前検査
現在、建築物の解体や改修工事を行う際は、アスベスト含有建材等の使用や吹き付けの有無を調べる事前調査を行うことが義務付けられています。この事前調査は所定の資格所有者が行い、アスベスト含有建材を使用している場合は、その種類に応じた方法で撤去します。
これらは無資格では行えないため、アスベストに関する事前調査及び対処については、専門業者に依頼してください。
解体工事前にアスベストに関して事前調査することは、現在、必ず行うことになっています。それについて、こちらのコラムで詳しく解説していますので、どうぞお読みください。
自分で家屋を解体するために必要なこと
家を自分で解体しようとする場合、それが古民家であっても、まだ築年数の浅い家であったとしても、共通して知っておくべきことがあります。それについて説明します。
こちらのコラムでも、DIYによる家の解体について解説しています。どうぞ参考になさってください。
家屋の解体、自分でしてもいいか?
そもそも、専門業者が作業に当たることが多い“解体”という作業を、一般の人が行っていいのか? という点に疑問を抱く方がいらっしゃるのかもしれません。
自分で自分が所有する建物を解体する場合、とくに何かの許認可を得る必要はありません。ただし、実際に解体工事を行っていくためには、次に説明するいくつかの手続きが必要になります。
必要な手続き
【工事前に行う申請や手続き】
・建設リサイクル法の事前申請
これは正式名を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、分別解体や再資源化、資源の有効利用、そして廃棄物の適正な処理を行うことを目的としていま
す。
対象となるのは建築物の解体工事、新築、増築、修繕、リフォーム、その他の土木
工事などです。これらの工事ごとに届け出の対象となる基準が決められています。解
体工事では、延べ床面積80㎡以上の建築物がこの法律の対象となり、次の書類を整
えて自治体の担当窓口に、工事着工の7日前までに提出します。
届け出書、分別解体等の計画表、工事の工程表、工事場所の地図、建築物全体がわ
かる写真、届け出を委任する場合は委任状、これらの写し。
・ライフラインの停止手続き
・道路占用許可
・近隣への挨拶と説明
・その他
【工事後に行う申請や手続き】
・建物滅失登記
・マニフェスト伝票の回収
・近隣へ工事終了の知らせとお礼
・その他
家屋の解体の流れに沿った解体計画
家屋の解体は、解体する建築物に違いがあったとしても、基本的な流れは共通しています。それらを理解したうえで、解体する建築物の特徴を考慮した解体計画を立てる必要があります。
これは前項で取り上げているように、建設リサイクル法の事前申請に必要であるとともに、「自分のペースで行うから」といって無計画や計画を無視した進行では事故やケガを起こしかねず、危険です。
【家屋の解体の流れ】
・足場や養生を設置
これは作業の安全確保と解体工事による周辺への影響を少なくするために欠かせないものです。
・家屋内部、続いて屋根、そして建物本体の解体へと進める
はじめは内装材や設備類の撤去から始め、屋根、建物本体、そして最後は基礎部分の解体へと進めていきます。
・地中埋設物やガラを撤去
以前、解体した際の瓦礫や浄化槽などの地中埋設物が発見されることがあります。その場合は、整地前にしっかりと撤去します。
・清掃と整地を行う
建物が建っていた場所以外にも敷地内をきれいに清掃し、整地して終了となります。
必要な機材・道具類
解体工事ではさまざまな機材や道具が必要になります。
チェーンソーや電動のこぎり、はつり機、バール等が基本的な道具となりますが、それに加えてショベルカーや小型移動式クレーンが必要になる場合があります。さらに、作業に当たる際の装備として、ヘルメット、安全靴、防護メガネ、防塵マスク、作業グローブなどがあります。これらの装備は、解体作業によって発生する粉塵や飛散物から体を守る面からもとても大切です。
DIYを趣味としている人であればこれらの基本的なアイテムは所有していると思いますが、ショベルカーや小型移動式クレーンなどを所有している人は少ないのではないでしょうか。さらに、それらの操作には「車両系建設機械の運転免許」が必要です。また、廃材などを運搬するためにトラックを使用する場合には、大型もしくは中型車両の運転免許も必要です。
これら重機類のレンタル、そして操作に必要な免許を所有していない場合はオペレーターなども手配しなくてはなりません。
解体工事では、さまざまな重機を使用します。こちらのコラムでは、その重機に関する情報をまとめていますので、よろしければこちらもお読みください。
作業の留意点
安全に作業を行うためには、最低限、次のことに留意しましょう。
・道具や必要物品をそろえるとともに、手伝いの作業員を確保する。
安全に作業を進めるためには、現場の状況に合った道具をそろえるとともに、作業員としてご自身と一緒に作業を行ってくれる人員を確保するといいでしょう。なお、その場合、作業員として加わってくれる人は、解体工事の経験がある人やDIYの経験が豊富な人がお勧めです。
・作業スペースをしっかり確保する。
解体作業では、解体した廃材を置く場所や重機などを駐停車しておく場所が必要で
す。また、廃棄物は分別して種類ごとに処分場へ運搬するため、保管場所としてゆとりのあるスペースを確保しておくといいでしょう。
・近隣への挨拶と説明を事前に行っておく。
ご自身で行うにしても、業者に依頼するにしても、家屋の解体工事では隣人をはじめとした近隣の方々に騒音や粉じんなどで迷惑をかけることになります。
そのため、事前に近隣の方々に工事を始めることと工事期間などを説明し、協力のお願いを含めた挨拶を行います。
廃棄物の処分
ご自身で家を解体した場合の廃材等の扱いはアスベストのような特殊なものを除いては、一般ごみの扱いになります。そのため、原則、解体する家屋が所在する自治体のルールに沿って廃棄します。
なお、家屋解体後に分別した廃棄物は次の方法で処分可能です。
・自治体のゴミ回収時に一般ごみとして出す。その際、ゴミ回収車が収集しやすいようにゴミ袋に納めて収集場所に廃棄。
・粗大ゴミとして自治体の回収に出す。
・ゴミの種類に応じた自治体の処理施設にご自身で搬入する。
・梁や太い柱などは専門とする業者に持ち込む。
・不用品回収業者に依頼する。
解体工事における廃棄物の取り扱いの基本について、こちらのコラムで解説しています。どうぞ参考になさってください。
古民家の解体は自分でできるか?
ここまで、主に一般家屋を自身で解体する場合について記してきました。では、解体するものが“古民家”であったらどうでしょうか?古民家の場合について考えてみたいと思います。
マトイでは、東京・埼玉・神奈川・千葉を中心に解体工事等の事業を展開しています。家の解体をご検討中であるものの具体的なプランについてお迷いの方も、どうぞマトイにお声掛けください。迷っている部分などについてもアドバイスやご提案をさせていただきます。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
古民家の定義
そもそも“古民家”とは具体的にどのようなものなのでしょうか。その定義は少し曖昧なようです。
一般的には、築50年以上経っている民家を「古民家」と呼んでいます。
しかし、築50年程度の古民家と、100年以上経っている古民家ではその構造や趣は異なります。築50年程度の古民家は、比較的、現在の家屋と共通する点がみられます。しかし、築年数がさらに経っていくと伝統工法で建てられたものが多くなり、前項の「業者に依頼するのと自分で解体するのとの違い」で説明している古民家の「造り」の特徴を含んでいます。
古民家と現代の一般家屋の解体の違い
古民家と現代の一般家屋の解体との違いでは、「構造」と「建築材料」の点で現在の建物の解体とは異なる難しさがあります。
伝統工法で建てられている古民家は、太い柱や梁が複雑に組み合わさって造られています。これを安全に取り外すには、伝統工法による構造を熟知した慎重な作業が必要になります。
また、建築材料の面では、現在の家屋では石膏ボードと断熱材で造られているような部分が、無垢材、竹、土壁、漆喰などの材料を用いて造られています。こちらについても解体においては専門的な知識や技術が求められます。
DIYによる古民家解体のリスク
古民家は築50年以上経過している家屋で、そのなかには100年を超えているものも少なくありません。それだけの年月を経ている建物を解体すること、とくに解体業者でないアマチュアが解体するには、以下のようなリスクがあります。
【安全面でのリスク】
このリスクがもっとも心配なものです。
古民家は築年数を重ねていればいるほど、建材などが腐敗したり傷んだりしてもろくなっている可能性が高くあります。そのため、解体中に作業の刺激によって想定していなかった部分が突然崩壊する可能性があります。
高所作業や重機を使用しての作業中はとくに注意が必要です。作業者や現場付近の通行者、そして隣人にケガを負わせたり、隣家の外壁や庭などを傷つけたりする可能性もあることを理解し、ケガや事故を起こさないように万全の対策をとる必要があります。
【環境面でのリスク】
解体工事では騒音や粉じん、大量の廃棄物の発生などがあり、環境への配慮が欠かせません。
とくに古民家では、現在は使用が禁止されているアスベスト含有建材や鉛を含んだ塗料などが使用されている場合があります。もしも、それらに対して解体時に誤った対処を行ってしまったら、作業者だけでなく周辺の人々にも影響を与えてしまいます。
アスベストでは義務付けられている事前調査を必ず行うこと、塗料などについても安全性がわからない場合は専門業者に相談するなどして、安全な処理が必要です。
【経済面でのリスク】
解体費用を安くするために自分自身で解体することを選ぶ人もいるようですが、実際には当初の予定以上に費用が高くなってしまうことがあります。
まずアスベストの事前調査費用、重機を使用する際のレンタル費用、重機を操作に必要な免許取得のための費用もしくは免許を取得しているオペレーターに依頼した際の日当などもかかってきます。
解体工事にはさまざまなリスクが伴います。リスク回避の第一歩は、施主様と業者とのコミュニケーションがしっかりと取れること。施主様から業者へ行う確認事項について、こちらのコラムでまとめています。どうぞお読みください。
DIYで古民家の解体をするのにかかる費用
では実際にDIYで古民家の解体を行うのに、どのくらいの費用がかかるでしょうか?
具体的には解体する古民家の大きさ、解体にかかる期間、使用する機材や道具、廃棄物の廃棄方法などによって変化してきます。
基本的にかかる費用として次のようなものがあります。
【解体作業員の費用】
解体作業員としてはご自分と一緒に手伝ってくれる人が必要です。
ご自身については、日当を支払うことはないとしても、本来の仕事を休んで解体作業に充てていることから、1か月の手取り給料を日割りした額に解体日数をかけた金額がかかっていると考えられます。
例えば、本来の仕事で月の収入が手取り40万円で、7日間かけて解体工事をしたとします。
40万円÷20日=2万円/日 解体期間7日×2万円=14万円
手伝ってくれる人の日当も必要になります。実際の解体工事の作業員の日当は、2万円以上です。現場の難易度や危険度によってさらに高くなります。しかし、DIYの場合は施主の考えや懐事情、そして相手の希望等によって決まります。ここでは15,000円で計算します。
15,000円×7日間=10万5,000円
以上の計算から、解体期間7日間、作業員2人の費用は24万5,000円となります。
【工事車両の費用】
基本的な道具類はそろっているものとして、ここでは重機のレンタル料を考えてみます。ショベルカー(小型)を7日間、廃棄物を処分場に運搬するためにトラックを7日間レンタルするとします。
・ショベルカーのレンタル料金 1万円×7日間=7万円
・トラックのレンタル料金 1万5,000円×7日間=10万5,000円
以上の計算から、解体期間7日間の重機等工事車両のレンタル料金は17万5,000円となります。
これらの重機等のレンタルについては、保険料・管理料・運搬料・燃料などの費用が別に発生する場合があります。また、車両のタイプや大きさ・積載量などによっても費用が異なります。ここで計上した金額は、あくまでも目安としてご覧ください。
【アスベストの事前調査費用】
これは義務として行わなくてはならないものです。アスベストの事前調査は書面検査、目視検査、分析検査の3段階に分かれていて、各検査の費用の目安は4万円~と考えておくといいでしょう。
なお、分析検査はアスベスト含有が書面検査や目視検査ではっきりできない場合にサンプルを採取して行うものです。必ず行うとは限りません。
【廃棄物の処理費用】
ここで例を挙げて詳しく説明することは避けますが、4tトラック5台分の廃棄物の処分では、20万円以上の費用がかかります。
【許可申請費用】
許可申請に伴う費用は、自治体によって異なりますが、おおよそ次の通りです。
・建設リサイクル法の事前申請:無料
・道路占用許可:2,000円前後
・建物滅失登記:自分で行う場合は1,000円前後、土地家屋調査士に依頼する場合4万円~
【費用のまとめ】
上記で示した、必要な費用をまとめると次の通りです。
・作業にかかる人件費(2人分):24万5,000円~
・重機やトラックのレンタル料金:17万5,000円~
・アスベスト事前調査費用:8万円~
・廃棄物処理費用:20万円~
・許可申請費用:4万円~
これらの金額はあくまでも、DIYによる解体にかかる費用の最低金額としてとらえておくといいでしょう。
自分で解体を行う場合の費用は、施主となる人がどの程度の必要機材や重機類およびそれら操作に必要な免許等をもっているか、解体する家屋の大きさ、一緒に作業をしてくれる人の人数等によって大きく異なります。
古民家の解体は業者に任せた方が安心
ここまで費用を含めて古民家をご自身で解体することに関する説明をしてきました。
そのなかで、建物の実際の広さ、大きさ、作業を手伝ってくれる人の人数、レンタルや追加購入が必要な工具など、それぞれご自分の計画に沿って各費用を見積もることで、具体的な計画をすすめることができます。
しかし、計画できないものが1つあります。それは安全を脅かすリスクです。万全の計画、万全の準備を整えて事故やケガのリスクを減らすことはできても、ゼロにはできません。そして万が一、事故やケガを負ったとしたら、場合によっては業者に依頼した場合の費用を上回るくらいの負担を負うことになりかねません。
この点から、古民家の解体をDIYで行うことはお勧めしません。
とくに古民家の解体は私たち解体業者にとっても、難易度の高い仕事です。どうぞ安全第一に、十分な検討を重ねたうえでの判断をなさってください。
まとめ
解体工事をご自身で行うことは、DIYを趣味にもって腕に自信のある方であれば可能なことです。しかし、そこには事故やケガを招く多くのリスクが潜んでいることをご理解いただきたいと思います。
よく「自己責任」ということをいわれます。もちろんDIYにおける事故やケガは自己責任となります。しかし、その程度によっては自己責任では片付けきれないものがあります。それは、解体業を生業としている私たちだからわかることです。
どうぞ、解体をご検討中の方は無理のない計画を立ててください。また、解体工事のなかには、業者が入る前に施主様やそのご家族でできる規模の解体がある場合があります。例えば庭に設置された物置や庭の植栽の撤去などです。これらをご自身で行うことで、費用を削減することも可能です。
マトイでは、そうした皆様のお考えやご希望も考慮した解体計画をご提案いたします。どうぞ、率直なご意見をお知らせください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
希望に合った良い解体業者の選び方は?
Next
2025年、要チェック! 古家解体時の高額費用に補助金を!!









