区画整理で家を解体。どんなことが必要? そして補助金等はある?
かいたいコラム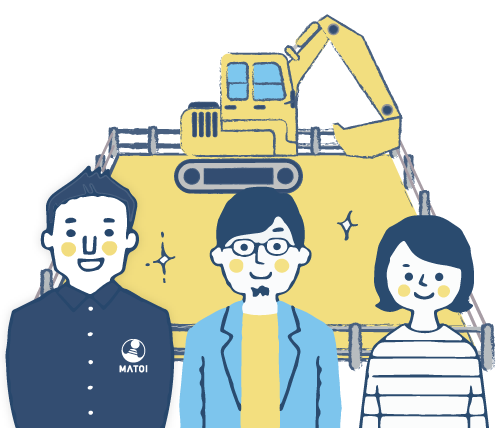
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
家を解体する理由の多くは、住まなくなった家を処分する、もしくは建て替えるといったことが主な理由でしょう。
しかし、それ以外の理由もあります。それが「区画整理」です。
今回は、この「区画整理のために家を解体する」といった場合について、その流れや必要になる費用などについて説明します。
家を解体する理由の1つ、区画整理とは?
「区画整理のために立ち退く」といったことをときどき耳にすると思います。この「区画整理」とは、どのようなことでしょうか?
これは正式には「土地区画整理事業」といい、道路や公園といった公共施設の整備や宅地の利用増進を目的とした事業のことです。
家が密集していて狭い道幅で防災的な問題を抱えている地域の道路を広げる、入り組んだ道を整備して人や車両の流れをよくする、公園などの公共施設を作る、このように、人々の安全や生活の利便性を向上させるために行われます。
区画整理によってその地域の利便性や安全性が向上し、土地の資産価値が高まります。
気になる区画整理の費用
土地の資産価値が高まるといっても、そのために立ち退きや敷地や建物が削られる家の人は大変です。
とくに気になる点は家の解体費用や引っ越し費用、そして新たに家を建てるための費用など、お金に関する諸々は心配になることでしょう。そこで、区画整理の協力対象となった方々が思う疑問について説明します。
マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の解体工事をお請けしています。家屋の解体工事のさまざまなご相談、そしてご自宅等の解体費の相場の把握などに、ぜひマトイの無料ご相談・お見積りをご利用ください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
そもそも解体費用等はだれが支払う?
区画整理はおもに行政の計画に基づいて行われます。そのため、区画整理によってそれまで居住していた場所を立ち退いたり、空き家となった家を解体撤去したりするための解体費用等は行政機関が、その対象となる地権者や居住者に支払います。
このときに立ち退き料が支払われますが、これは「補償金」といった位置づけとなり、次の費用が含まれます。
・代替地の準備費用:住まいの場となる新しい土地を準備するための費用。
・建物の解体費用:立ち退いて空き家となった家の解体費用。
・建物の建築もしくは移転(曳家や再構築工法)費用:新たな住まいを新築する、もしくはそれまで住んでいた家を移転するための費用。
・引っ越し費用:新たな場所への転居にかかる費用。
・仮住まいの費用:立ち退き先の家が出来上がるまで、もしくは移転が完了して住める状態になるまでの間の賃貸住宅の費用。
自己負担金は発生する?
基本的に区画整理に伴う転居やそれまで居住していた家の解体費用等の支出全般は、立ち退き料に含まれ、行政が負担してくれます。そのため、原則として自己負担金は発生しません。
ただし無茶難題をいって非協力的な姿勢をとっていると立ち退き料に影響が出たり、場合によっては損害賠償を請求されたりすることがあるようです。
解体工事の保証金や補助金・助成金制度はある?
区画整理ではなく、空き家や老朽家屋等を解体する際、家屋が所在する自治体に補助金等の制度がある場合は、解体工事に対して補助金や助成金を活用できます。
区画整理の場合にそういった補助金や助成金制度があるか、あったとして使えるかということを考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、区画整理の場合は前項のように立ち退き料に解体費用も含まれているため、解体工事に対する補助金等の制度はありません。
区画整理による家屋解体や立ち退き等の流れ
区画整理によって家屋解体や転居等をするまでの流れは、一般的な理由によるときとは少し違います。そこに至るまでの流れは次のように進められます。
通常、家屋解体はこちらのコラムにあるような流れを踏んで、解体工事に取り掛かります。
計画決定と住民説明会の実施
そもそも区画整理は、地域のまちづくりの一環として行われます。地元住民と行政との話し合いによって区画整理が必要なものについての案を検討し、区画整理事業の施工区域を決定します。その後、資金計画や設計、事業期間等の計画を行政が決定していきます。
この段階で対象区域となる住民に対して、区画整理の計画を伝え、事前に周知を図ります。これは、スムーズに計画を進めるために欠かせないものです。こうして計画を決定したら、住民に向けての説明会を実施します。
説明会では改めて区画整理計画の周知徹底に向けた説明を行うとともに、区画整理の対象となる住民(地権者)の同意を得るための手続きを行います。
同意を得られない住民に対しては、個別交渉を進めていきます。しかし、正当な理由がないまま決められた期限までに同意しない住民に対しては、直接施工(強制執行)や損害賠償責任が生じる可能性があります。
土地区画整理組合の設置
区画整理計画が決定して住民説明が終了したら、「土地区画整理組合」を設立します。
組合の設立には、区域内の宅地所有者および借地権者の3分の2以上が事業計画に同意する必要があります。そのうえで区域の宅地所有者、借地権者による原則7人以上の組合員が集まり、都道府県知事の認可があれば設立できます。
行政、区画整理組合、区画整理の対象となる住民の3者の関係と役割は次の通りです。
【行政の役割】
・まちづくりに関する計画の決定や事業の認可。
・区画整理事業の進行の監督。
・住民への説明会を開催。
・補償や移転等の支援提供。
【土地区画整理組合の役割】
・土地の整理や換地計画を実施。
・それに伴う住民との調整。
・立ち退き等が必要な場合の補償金の支払い。
【区画整理の対象住民の役割】
・区画整理に伴い立ち退きや家屋解体等の求めに対し、補償金や新たな土地の割り当てを受ける権利をもつ。
・行政や土地区画整理組合と協議しながら、区画整理のために必要な立ち退き等を実施。
仮換地指定と建物移転補償交渉
実際に立ち退きや家屋解体などを行う前に、区画整理組合と対象住民が新たな暮らしの場となる場所(仮換地)とそのための補償の交渉を行います。
仮換地は土地区画整理計画に基づいて位置や面積が決定され、対象者の意見を聞いて計画を調整しながら決定します。
さらに移転対象となる建物の構造や仕様等を調査し、移転に必要な費用を算定。その額を補償金とするとともに、そのほかに必要な支援を含めた補償内容を協議します。
仮換地指定や建物移転等に関する補償内容に合意し、契約をかわしたら、交渉は完了します。
立ち退き
前述までのプロセスが完了したら、立ち退きのための引っ越しを行います。
立ち退きに必要な費用は、原則として建物を明け渡す日に支払われます。これは事前に支払った場合、住人が退居日を守らないといった事態を避けるためです。
しかし、実際には行政や組合との話し合いなどによって引っ越し費用として補償金の一部が事前に支払われたり、行政によっては立ち退きの前後に分けて補償金を支払ったり、というケースもあります。
解体工事の支払いに関する情報をこちらのコラムでまとめていますので、参考にご覧ください。
工 事
対象者が無事に立ち退くと、家屋等の解体工事を開始します。
なかには古民家のような年月を重ねているものの頑健な家屋や、とくに深い愛着をもつことから住人が希望する家屋など、解体するのではなく、曳家工法などによって家屋を移動することもあります。
これらの既存家屋を含めた建築物の解体撤去が済むと、土地区画整理計画による新たなまちづくりの工事に移り、利便性の高いまちが作られます。
曳家をはじめとした家屋を解体しないで移築する方法について、こちらで説明していますので、ご興味のある方は参考になさってください。
換地処分
交渉段階の仮換地は、登記上は他人の土地であっても仮換地として使えます。そして立ち退きが終わってから、換地処分を行います。
換地処分によって仮換地の所有権を取得し、もともと所有していた土地とみなします。
土地および建物の登記と清算金の交付
換地に移って建物も代わるため、土地や建物の新たな登記が必要になります。これは、施工者がまとめて行ってくれます。
これらが行われてから清算金の交付が行われます。
清算金は、区画整理前の土地と新しい土地の価値に差によって支給されたり、徴収されたりする金額をいいます。以前の土地の評価額が新しい土地の評価額よりも高い場合は、精算金が交付されます。逆に以前の土地の評価額が新しい土地の評価額よりも安い場合は、精算金を徴収されます。
こうして清算金の交付や徴収を行うことで、利害の差をなくします。
区画整理の知らせを受けたら行うことは?
区画整理の対象者となると、行政から通知が届きます。突然、立ち退きや住居解体に関する知らせを受け取った人は、どうしたらいいか戸惑うことでしょう。
そこで、区画整理の対象となった通知を受け取ったら、どのように対処を進めていったらいいのか、その流れを説明します。
「区画整理で立ち退いて、家を解体しなくてはいけない!」そんなとき、解体工事についてマトイにお気軽にお問い合わせください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
区画整理を正しく把握するための用語の理解
区画整理の通知や行政担当者や区画整理組合とのやり取りでは、聞きなれない用語が出てきます。受け取った通知の内容の理解や行政担当者などとの対話を円滑にするためにも、基本的な用語を理解しておきましょう。
○保留地(ほりゅうち)
土地区画整理事業によって生み出された土地で、施工者などの事業主体者が取得する土地です。これを売却することによって事業主体者は事業費の一部に充てます。
○減歩(げんぶ)
土地所有者が公共施設の整備や事業費の調達のために、土地の一部を提供することです。なお関連する用語として次のものがあります。
・公共減歩:公共施設の整備のために提供される土地。
・保留地減歩:事業費を賄うために売却される保留地のために提供される土地。
・減歩率:減歩する土地の割合を示す指標。
減歩によって所有する土地の面積は減少するものの、区画整理によって利便性が高くなることで土地の価値は上昇するため、所有者にとって損失は生じないとされています。
○換地(かんち)
土地の所有者が区画整理前の土地を区画整理事業に提供し、その代わりに整理後の土地を割り当てられるものです。なお、区画整理事業において、区画整理前の土地を従前地といいます。
換地は従前地の位置や面積、利用状況等を考慮して確保され、公平性が確保されます。そのため換地の価値が従前地の価値と異なる場合には、不公平性の是正のために精算金が交付、もしくは徴収されます。
○仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業が完了するまでの間、従前地を使用できない場合に代替地として提供される土地をいいます。
移った人はここに建物を建てたり、貸し出して収益を得たりする権利が認められ、事業完了後に正式な換地に移行すると、従前地の権利は消滅します。
○立ち退き料(たちのきりょう)
区画整理事業のために住民が従前地から移転を余儀なくされる場合に支払われる補償金をいいます。具体的には次のような費用が含まれます。
・建物の移転に関連する費用として建物の解体や新築または移転先の購入費用。
・引越し費用:家財道具の運搬や新居の準備にかかる費用。
・営業補償:店舗や事務所の場合、移転による売上減少や内装費用の補償。
・仮住居費用:新しい住居が完成するまでの間、一時的な住居の賃料。
○建物滅失登記(たてものめっしつとうき)
通常、所有する建物を解体撤去した場合、その建物の登記も抹消します。これを建物滅失登記といいますが、区画整理によって建物を解体した場合にも、同様に行います。
通知内容を確認
住んでいる場所が区画整理の対象となった場合、行政から区画整理の協力を求める通知が届きます。まずはその内容をしっかりと確認することが大切です。通知内容は一般的に次のことが記されています。
・区画整理事業の目的、背景、地域の整備計画の概要。
・事業への協力を依頼する内容。
・必要な手続きやスケジュール、提出書類など。
・問い合わせ窓口。
なお、土地の移転や換地に関する具体的な計画も示される場合があり、通知の内容は地域や事業の規模によって異なります。内容についてより具体的なことを知りたい場合や疑問点は、自治体の担当部署に問い合わせるようにしましょう。
必要書類の準備と提出
区画整理の対象となった場合、一般的に次の書類を求められます。必要なときに慌てず提出できるように、通知を受け取った段階から準備するようにしましょう。
○土地の所有権に関する書類
・登記簿謄本や土地の権利証明書。
・土地の境界に関する資料。
○建物に関する書類
・建物の図面や固定資産税評価証明書。
・建物の所有権を証明する書類。
○住民票や身分証明書
○換地計画に関する同意書
○補償金受け取りに必要な銀行口座情報や同意書、など。
現地確認や立ち会い
補償金や精算金などのために区画整理予定地の現地確認やその際の立会い、行政担当者との面談などが必要になる場合があります。
それによって、解体予定の建物や土地の状況などを確認し、情報を共有します。
こちらのコラムに現地調査の立ち合いのポイントを詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
立ち退き準備
区画整理の対象となって区画整理計画や提示された仮換地や補償金等の条件に納得できたら、転居先の手配や解体業者との日程調整など、立ち退きの準備を始めます。
なお、引っ越しおよびそれらにかかる費用など、行政や区画整理組合から提供される補償内容やサポートを確認し、活用します。
引っ越しや解体工事前の不用品等の処分は一苦労です。こちらのコラムで処分のコツ等について説明しています。どうぞお読みください。
近隣住民への挨拶
区画整理計画については近隣住民も同様に周知しているはずですが、対象者として立ち退く際には、事前に近隣の家々に挨拶をしておきましょう。
引っ越しやそれに続く家屋の解体工事などによって、近隣の家々にも何らかの影響が考えられます。挨拶をするなどの配慮を心掛けておくことで、後々のトラブルを防げます。
必要な手続きの対応
建物滅失登記や固定資産税の変更申請などの手続きが必要になる場合があります。どのような手続きが必要になるかは、区画整理計画にどのような協力をするかによって異なりますので、行政や区画整理組合と相談しながら進めましょう。
区画整理による家屋解体はどこまで? 基礎も解体撤去する?
区画整理では家屋を解体撤去する場合、迷うことの1つに基礎部分もすべて解体撤去して更地にするか否かという点があります。実際に解体業者との事前の打ち合わせでは、基礎部分も含めて解体して更地の状態にするか、基礎部分は残しておくかという点も含めて解体計画を立てます。
これについては、一般的に行政が判断しますので行政担当者や区画整理組合に確認する必要があります。基礎が残っていても区画整理計画を進めるのに問題がなければ、行政は“基礎部分の解体の必要ない”と判断します。
ただし、行政や組合からの返事が“基礎部分の解体は不要”だとしても、建物によっては基礎の立ち上がりを取り壊す必要があります。そのため上部構造だけの解体工事だとしても、解体業者に基礎部分への影響の有無を含めて基礎部分の解体工事をしたほうがいいかどうかの確認をとっておく必要があります。
そして基礎部分の解体では、廃棄物処理の問題が大きく関係してきます。基礎部分を残して、そのまま地中埋設物となる場合は廃棄物処理法に抵触する可能性があります。さらにその土地の不動産価格も低下しかねません。
この点も踏まえて、可能であれば行政や組合と話し合いのうえで、基礎部分も解体することをお勧めします。
区画整理の所要期間
区画整理にかかる期間は、その規模や地域の状況によって大きく異なります。多くは10年から20年程度ですが、内容によってはさらに長期間になるものや、短期間になるものもあります。
一連の期間の内訳は次の通りです。
・計画を策定のための期間。
・土地所有者や住民との合意形成、その手続きのための期間。
・建物の解体や移転にかかる期間。
・インフラ整備の期間。
・全体の完成と引き渡しの期間。
まとめ
区画整理の対象となった場合、原則としては行政や区画整理組合の要請に従わなくてはなりません。
住み慣れた場所や愛着のある家を離れたくない思いはあると思いますが、区画整理によって地域の利便性や資産価値は高まります。また、移転に必要な転居費用や解体費用などの費用の自己負担は生じません。
これらを含めて区画整理の意義や流れを正しく理解したうえで、行政や区画整理組合とコミュニケーションを図りながら進めていくようにしましょう。
なお区画整理による解体工事は何か特別なものがあるのかも?と思いがちですが、解体工事自体は他のケースと変わりません。マトイでも区画整理による解体工事やそれに関するご相談も受けております。どうぞお気軽にお声かけください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!
- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!
- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!
ご相談・お見積りは無料です。
どのような内容でもまずはお気軽に
お問い合わせください!
電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付
Preview
解体後に土地を売りたい! 売却時の解体費用はいくらになる?
Next
超解説!解体現場~一目で分かるやさしい現場コラム~







